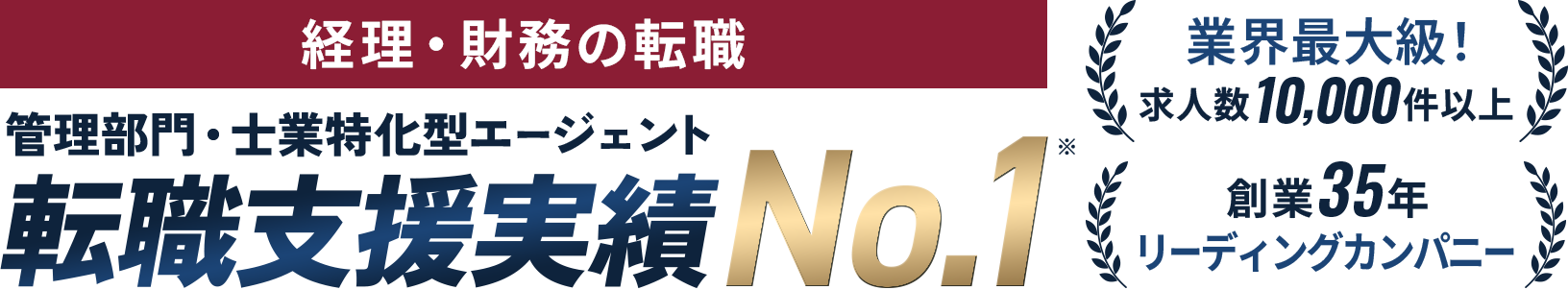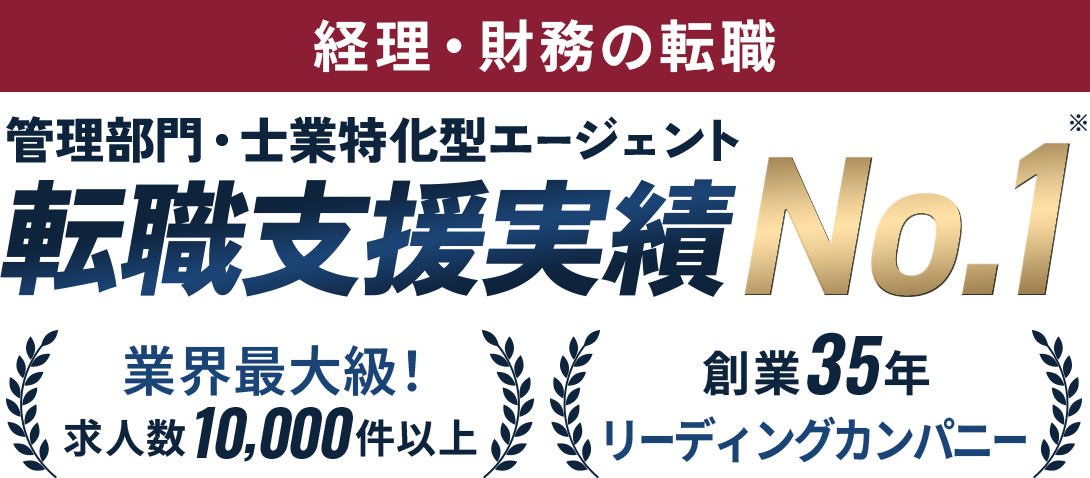※厚生労働省「人材サービス総合サイト」における管理部門・士業領域に特化した有料職業紹介事業者の「無期雇用および4ヶ月以上の有期雇用の就職者数」(2024年度実績を自社集計)による。なお、管理部門・士業領域への特化の有無は、当社において比較対象の有料職業紹介事業者のウェブサイトを全件閲覧して判断。(2025年8月1日時点)
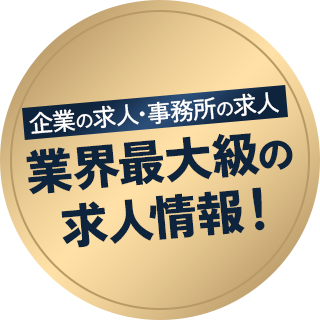
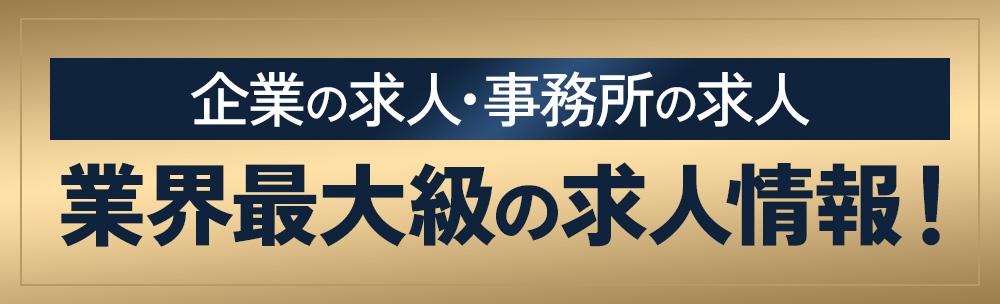
経理・財務が
MS Agentを利用するメリット
- 創業から30年以上、豊富な経理・財務系キャリアの転職サポート実績があります。
- 業界トップクラスの実績を誇る管理部門特化型エージェントとして、質の高いサービスをご提供します。
- 大手上場企業からIPO準備企業など幅広いニーズにお応えできます。
求人検索&転職セミナー
業界最大級!経理・財務の求人検索
こだわり条件多数!求人特集
経理・財務の転職セミナー・個別相談会
経理・財務の方のためのイベントやセミナー、個別相談会を開催しています。
-
30代。キャリアも安定も重視したい!長く働ける1社に出会う為の個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く -
【横浜】30・40代経理・財務人材向け!理想の環境が見つかる!経理・財務専門キャリアアドバイザーとの個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く -
【名古屋】土曜相談可!3か月以内に転職を希望される経理・財務職の方向けの個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く -
【大阪】転職を中長期で考えたい経理・財務職の方の為の個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く
キャリアパスと転職成功事例
経理・財務のキャリアパス
経理・財務の方が活躍できる6つのキャリアフィールドをご紹介。
管理部門特化エージェントである弊社がそれぞれの採用動向をまとめましたのでご確認ください。
経理・財務の転職成功事例
経理・財務の転職成功事例をご紹介します。 ※随時更新
- NEW ワークライフバランスの改善とキャリアアップの両方が叶うIPO準備企業へ転職された方の事例
- NEW キャリアアップの為、税理士事務所から上場企業経理職へ転職成功した事例
- NEW 転職の成功は求人票の枠を超える!求人票の記載年収から大幅アップで決定されたミドル人材の事例
- NEW スキル向上と自己分析の準備で、会計事務所から大手企業経理に転職した事例
- NEW 子育て中のママさんが叶えた、柔軟な働き方ができる経理職への転職事例!
転職ノウハウ
経理・財務版 転職活動の基礎知識
~転職活動は段取りが全て~ 転職活動を始める前に知っておきたい「転職活動の流れ」をご紹介いたします。


転職を始める前に知っておきたい6つのこと
経理・財務の転職FAQ
経理・財務の職務経歴書

経理・財務特有の経歴を上手くまとめる事が、書類選考通過には重要です。職種毎に異なるアピールポイントを意識して書いた職務経歴書と、意識せずに書いた職務経歴書では、たとえ同じ経歴であったとしても評価に大きな差が出ます。各職種特有のポイントを押さえ、魅力的な職務経歴書を作成しましょう。
職務経歴書の書き方 ポイント解説はこちら業界トピックス
経理・財務向け 業界トピックス
業界情報や転職に関する情報等さまざまなトピックスを発信しています。
転職をお考えの方もそうでない方も、ぜひご覧ください。
-

経理の転職完全版|求人情報・転職理由・志望動機・面接対策まで徹底解説
この記事では、35年以上に渡り経理・財務人材の転職を支援してきた管理部門・士業特化型転職エージェント「MS-Japan」が教える経理の転職ノウハウやオススメ求人を紹介しています。 企業規模・業種を問わずニーズの高い経理だからこそ、市場価値向上や働き方・待遇改善などのために最新の転職市場や求人情報はこまめにチェックしましょう。 ▼この記事のまとめ 経験者向け経理転職の3つのポイント 経理の実務経験者が転職の際に押さえるポイントは、 ・実務経験とキャリアプランが伝わる志望動機 ・企業が求めるスキルや経験の把握 ・年齢に合わせた自己PR 未経験者向け経理転職の2つのポイント 未経験から経理への転職を目指す場合は、 経理の役割や仕事内容を理解した上で、 ・経験をカバーできる資格 ・経理関連の業務経験の洗い出し を行いましょう! 転職エージェントを使って有利に転職を進めよう! 「MS-Japan」では、経理に精通したキャリアアドバイザーが業界最大級の求人数からオススメの求人をご紹介します。 「高年収求人」「大手企業求人」「リモート求人」「未経験可求人」など希望に合わせた求人を幅広く扱っています。 経理×高年収の求人・転職情報 【経理マネージャー候補】AItechベンチャー/働きやすい環境/IPO準備 仕事内容 ・売上請求書発行 ・仕訳起票 ・債権債務管理 ・月次、四半期及び年次決算業務、連結会計業務 ・開示書類作成支援業務 必要な経験・能力 ・経理実務経験が3年以上ある方 ・月次決算の締め作業の経験がある方 ・ExcelまたはGoogleスプレッドシートにて関数/ピポットテーブルの実務経験があること 想定年収 800万円 ~ 1,200万円 創業30年!直近10年黒字経営、業績好調の企業より経理部長候補 仕事内容 ・月次決算、年次決算の取りまとめ ・毎月の予実管理、分析、並びにレポーティング業務 ・税理士の監査対応 ・金融機関との折衝 (現在、9行の金融機関と取引があり、月に一度の月次決算の経営報告と年に一度の資金調達折衝を行っております) ・償却資産税申告書の作成 ・設備投資計画の作成とそれに基づく中期経営計画書 等 必要な経験・能力 ・年次決算の取りまとめ経験 ・固定資産税の知識又はご経験を有する方 想定年収 800万円 ~ 1,000万円 \転職活動は求人探しが一番大変/ 希望に合う求人を紹介してもらう 経理×リモートの求人・転職情報 大手通信会社子会社にて財務経理(リーダー候補)/リモートフルフレックス 仕事内容 ・年次/四半期/月次決算業務 ・伝票起票、債権債務管理、伝票審査から財務諸表3表作成など決算業務全般 ・監査法人対応 ・日次〜年次の入出金管理 必要な経験・能力 下記のいずれかのご経験 上場会社、IPO準備企業またはその子会社での単体決算実務(2年以上) 監査法人における企業会計監査のご経験 想定年収 648万円 ~ 780万円 【フルリモート相談可】IPO準備中企業の 経理マネージャー候補 仕事内容 ・月次・四半期・年次決算業務 の取りまとめ・チェック ・上場準備に伴う経理体制の構築(内部統制運用含む) ・経理業務プロセスの改善・効率化 ・監査法人・証券会社・顧問税理士との折衝・調整 必要な経験・能力 ・事業会社における決算経験をお持ちの方(目安3年以上) ・上場企業または上場準備企業における経理経験 想定年収 650万円 ~ 1,000万円 求人特集リモート可の経理求人を探す 経理×未経験可の求人・転職情報 <未経験歓迎>経理財務担当/グロース上場/フレックス・リモート制度有/スキルアップ◎ 仕事内容 ・日常経理 ・個別及び連結決算 ・税務(法人税や消費税を中心とした顧問税理士とのやり取り) ・開示業務(短信/有報/計算書類等の作成) ・監査法人対応 必要な経験・能力 ・社会人経験2年以上(第二新卒歓迎) ・日商簿記3級以上の資格取得者 ・Excel、Wordなどの基本的なPCスキル 想定年収 400万円 ~ 500万円 未経験から経理のキャリアをスタート!!地域に根ざした安定企業/管理部門全般に挑戦できる環境 仕事内容 ▼経理 決算、管理会計業務を中心に担当していただきます。 ・各部署から提出される伝票の管理 ・決算、管理会計等の資料作成から予実管理 ・給与計算 など ▼総務 ・車両管理 ・事務用品の発注 ・Pマーク対応 ・契約書チェック 必要な経験・能力 ・簿記3級以上の資格をお持ちの方 想定年収 400万円 ~ 650万円 業界最大級の求人数から探せます 経理×未経験可の求人はコチラ 「求人の詳細情報が知りたい」「求人に応募したい」という方は、MS-Japanにご登録ください。 経理に精通したキャリアアドバイザーが希望に合った求人をご提案し、求人の応募から選考対策、条件交渉まで一貫してサポートします。 \経理専門のアドバイザーが転職をサポート!/ MS-Japanで求人を紹介してもらう 経理の最新転職市場動向 経理の転職市場は、求人数が求職者数を上回る「売り手市場」が続くでしょう。 弊社取り扱い求人においても、経理の求人倍率は2021年以降右肩上がりです。特に経験者のニーズが非常に高く、各企業が即戦力人材の採用を強化しています。 一方で、未経験者向け求人も高水準を維持しており、増加ペースは緩やかながら着実に伸びています。 転職を検討する多くの方にとって、気になるテーマの一つは、出社回帰ではないでしょうか。 2023年5月のコロナ5類移行後、経理職でも出社頻度は増加傾向にあります。 一方で、一度リモートワークを前提にした生活スタイルに慣れた方、更には地方や郊外に転居した方にとっては、由々しき事態です。 そのこともあってか、リモートワークを導入した企業の多くはフル出社に戻すわけではなく、リモートと出社を組み合わせたハイブリッド勤務へ移行しています。 その他にもコロナ禍と働き方改革の流れを受けてフレックス制度を導入する企業も増えており、多様な働き方を受け入れる流れは止まっていません。 以上のとおり、転職市場においては2025年も求職者優位の状況が続く見通しで、経理で転職を検討している方にとっては、幅広い選択肢の中から希望に合った職場を見つけやすい市況が続くでしょう。 あわせて読みたい 経理は転職しやすい?経理の転職市場や主な転職先、転職成功のポイントを解説 \同期はもう転職活動を始めてるかも/ 今すぐ転職活動を始める 経理の年収をアップする方法は? 経理として転職を考えている方の中には、より高い年収を希望するケースも少なくありません。 実際、2023年にMS-Japanへ登録した経理転職希望者の約5人に1人が、転職理由として「年収アップ」を挙げています。 経理が年収アップを目指すうえで、特に重要なのは実務経験です。 日商簿記などの資格を取得すれば年収が上がるという情報を目にすることもあります。 しかし実際には資格取得をきっかけに担当領域が広がり、業務レベルが上がることで実務経験が積み重なり、結果として年収アップにつながるケースが大半です。 特に「決算業務」と「マネジメント」の経験はキャリアアップの大きな転換点になるため、現職で両方の経験を積めない場合は、転職が年収アップの有力な選択肢となります。 また、経理は個人で売上を直接生み出す職種ではないため、年収は企業の売上や利益に左右されます。 業界全体の年収水準が低い場合や売上規模の小さい企業では、どれだけ努力しても希望年収に届かないことがあります。 このような場合は、希望年収を実現できる業種・規模の企業へ転職することが年収アップへの近道となるでしょう。 あわせて読みたい 経理経験者が転職して年収を上げるには!?おすすめ求人も公開! 30代・40代の経理の市場価値は「決算早期化」で決まる|転職市場で評価されるスピードと正確性(後編) \同年代はもっと貰っている!?/ 転職で年収アップを叶える 経理への転職は難しいと言われる理由とは? 「経理の仕事内容」からも分かるように、経理の仕事はすべての企業で必要とされるため、管理部門の中では比較的求人が多く、常に需要がある職種です。 しかし、一部の方からは「経理の転職は難しい」という意見もあります。 経理への転職が難しいと言われる理由の一つは、経験が重視されるため未経験から挑戦しづらい点です。 経理で身に付けられる専門的なスキルは、業界や業種を問わず汎用性が高いため、いわゆる手に職が就く、つぶしが効く職種と言われており、未経験からキャリアチェンジを希望する方が多い職種です。 一方で、仕事がら知識に加えて、何より経験が重視されるため、未経験から挑戦しづらい職種と言えます。 未経験から経理に挑戦する場合は、まずは簿記2級などの資格を取得することと、積極的に未経験をうけ入れている中小企業や会計事務所なども、転職先として視野に入れる必要があります。 また、経理の転職が難しいと言われる理由のもう一つは、業界や業種、会社規模を問わず経理の求人は発生するため、求人件数が多い一方で、条件が良い企業に応募が殺到する傾向があります。 人気の求人には、企業経理の経験者に加えて、公認会計士や税理士といった士業も応募が集まります。 そのため、応募用件を満たしているにも関わらず、書類選考で見送りになることもあり、思ったように転職活動が進まず難しさを感じるようです。 特に、大手企業や年収水準が高い企業、リモートワーク・フレックス制度など柔軟な働き方が可能な企業は、競争率が非常に高い傾向にあります。 そのため、経理として一定の経験を積んだ方であっても、拘る条件が複数ある場合や高望みな希望を持っている場合は、転職が難しくなります。 あわせて読みたい 経理の転職は難しい?未経験・経験別に転職成功へのポイントをご紹介! \経理・財務特化の転職エージェント!/ MS-Japanに無料会員登録する 経理・財務の転職で後悔しないためには 経理・財務への転職をしたものの、想定と現実のギャップから「思っていた仕事と違った」と感じてしまう人もいます。 こうした後悔を防ぐためにも、以下のポイントを押さえておくことが重要です。 経験・スキルの棚卸しで適性を確認する 転職前には必ず自身の経験やスキルの棚卸しを行いましょう。 過去の職務経験を時系列で振り返り、実績やモチベーションが上がった出来事などを洗い出します。 スキルだけでなく、考え方や仕事の進め方なども明確にすることで、転職後も無理なく働き続けられるかどうかの判断がしやすくなります。 希望条件を事前に明確にする 年収や勤務地、残業の有無といった希望条件を明確にしておくことも欠かせません。 キャリア面で興味のある仕事でも、希望とかけ離れた条件では後悔につながる恐れがあります。 特に年収は生活に直結するため、妥協のしすぎは禁物です。条件を整理しておけば、求人選定や転職エージェントとのやりとりもスムーズになります。 入社前の情報収集でミスマッチを防ぐ 入社後の後悔を避けるためには、企業研究が不可欠です。 職場の雰囲気や残業状況、実際の業務内容が想像と異なっていた場合、ミスマッチを感じるリスクが高まります。 企業の公式サイトや口コミサイト、SNSなどを活用し、できる限り具体的な情報を集めることが大切です。 転職エージェントを活用する 経理への適性やキャリアに不安がある場合は、転職エージェントの利用も有効です。 特に、経理に特化したアドバイザーによるカウンセリングを受けることで、自分に合った求人を見極めやすくなります。 また、求人情報では分からない企業の情報も、転職エージェントから知ることも可能です。 さらに、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策の支援も受けられるため、転職活動全体を効率的に進められるでしょう。 あわせて読みたい 経理に転職して後悔…「こんなはずじゃなかった」をなくすための注意点とは \転職に不安があるなら/ 無料で転職サポートを受ける 経理の転職活動の進め方 初めて転職する場合や久しぶりの転職の場合、どのように転職活動を進めるか迷う方も多いでしょう。 ここでは、経理の転職活動に関する基本情報をご紹介します。 転職エージェントを活用した転職活動の流れ 転職をする際の主な手法には、次のようなものがあります。 ・転職エージェントの活用 ・転職サイトの活用 ・スカウトサービスの活用 ・企業の採用ページから直接応募 ・知人・社内紹介(リファラル) ・ハローワークや自治体の就職支援窓口 ここでは、転職エージェントを利用する場合の流れを見ていきましょう。 会員登録後はキャリアアドバイザーと日程を調整し、キャリアカウンセリング(面談)を実施します。 その後、これまでの経歴や希望をもとに、適切な求人が紹介されます。 紹介される求人には、一般には出回っていない非公開求人も含まれます。 企業の雰囲気や具体的な業務内容などの共有もあるため、不安を払拭しやすいでしょう。 また、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策のアドバイスが受けられ、書類提出や面接日程の調整も代行してくれます。 内定後は年収や入社日などの決め、退職に向けた準備の相談も可能です。 煩雑な手続きを任せられるため、在職中でも無理なく転職活動を進められます。 経理の転職でおすすめの時期はいつ? 経理の転職を考えている方の中には、時期を気にしている方もいるのではないでしょうか。 結論をお伝えすると、求人数の増減には波がありますが、同様に求職者の増減にも波があるため、求人倍率という観点では、求人が多い時期を狙うことが必ずしも転職を有利にするわけではありません。 特定の時期を狙うよりも、早めに準備を始めておいて、焦らずに転職活動することをお勧めします。 以下はあくまでも参考として、時期による求人の増減についてお伝えします。 まず、欠員補充の場合は時期によらず、退職予定者が出た時点での募集になります。 増員募集の場合、採用担当者は経理部門から人手不足の解消を求められて採用活動を行うため、経理部門の繁忙期の2~3か月ほど前に求人を出す傾向があります。 1年間の中で、最も業務が多く人手が必要な時期は決算時期であり、年度末決算より少し前に経理の求人が集中します。 日本企業の場合には3月末を決算とする企業が多く、5月末までに税務申告を終えなければならないため、1~2月に求人を出して4月の採用を目指す企業が多数見られます。 次いで、株主総会が終わる6〜7月頃も半期決算を控えているため、9月入社を見据えた経理求人が増える時期でもあります。 また、年末調整業務が行われる12月や四半期決算が行われる1月・7月・10月など増員・欠員の求人が発生するのも経理の特徴です。 上記のように、採用企業の業務スケジュールから逆算して、繁忙期となる2~3か月前には転職活動を開始できるよう、準備を進めておくとスムーズでしょう。 ▶詳しくはコチラ:経理の求人が集中する時期は?未経験者・経験者別に転職成功のポイントも紹介 在籍中に転職活動を進めた方がいい? 経理職の転職では、在職中に活動を始めるのが一般的です。収入が確保されているため精神的な余裕があり、職歴にブランクも生まれません。採用側からは「計画的で責任感がある」という印象を持たれることも多く、評価されやすい傾向があります。 一方で、仕事との両立は時間的に負担がかかるため、スケジュール管理や情報の取り扱いに注意しましょう。 職場に知られずに動くには、転職エージェントの活用などの工夫が必要です。 ▶詳しくはコチラ:在職中の転職活動はNG?メリットやデメリット、現職にバレないための対策など あわせて読みたい 経理の転職に「最適な時期」は?未経験者・経験者別に詳しく解説 「ホワイト企業の経理」に転職する6つのポイントとは ボーナスをもらってから転職はアリ?転職スケジュールや諦めた方が良いケースについて解説 在職中の転職活動はNG?メリットやデメリット、現職にバレないための対策など \経理・財務特化の転職エージェント!/ MS-Japanに無料会員登録する 経理への転職を成功させるポイント この章では経理への転職を成功させるポイントを3つ解説します。 経験とキャリアを明確にした志望動機 経理の転職では、「即戦力」として活躍できるかが重視されます。 採用担当者は、求職者が実務経験を積んでおり、即戦力として期待できるかを選考で判断します。 そのため、志望動機では企業が求める業務やミッションに結びつく具体的な経験をアピールすることが重要です。 また、これまでの経験だけでなく、転職後のキャリアビジョンを明確に示すことで、「なぜその企業でなければならないのか」が伝わる志望動機になります。 経理の転職選考で評価される志望動機については、次の章で詳しく解説します。 求められるスキル・経験を把握する 「経理の転職」といっても、求人によって求められるスキルや経験は大きく異なります。 実務の中でも財務会計と管理会計のいずれを重視するのか、税務や財務の経験を求めるのか、管理職としてのチームマネジメント経験を重視する求人もあります。 そのため、求人の募集要項から求められるスキルや経験を正確に把握し、自分の経験やスキルをどのように自己PRに結びつけるかを考えることが重要です。 また、経理の求人全般で求められるスキルや知識については、「経理の転職で求められるスキル・知識」の章で解説します。 自分の年齢に合わせたアピールポイントを押さえる 以前は「35歳、転職限界説」という言葉がありました。今でこそそこまで言われなくなりましたが、転職の難易度は年齢によって異なります。 それは、年齢を追うごとに経験値の積み上げが求められるため、自分の年齢に応じたアピールが求められます。 特に30代以上では、資格や知識だけでは足りない場合が多く、実務経験や具体的な成果が問われる傾向があります。年齢に応じた強みを明確にし、採用担当者に響くアピールポイントを準備しましょう。 年代別の経理の転職ポイントについては、「【年代別】経理転職のポイント」をご確認ください。 あわせて読みたい 経理の自己PR|経験者・管理職・未経験者それぞれのポイントや例文を完全解説! \転職に不安があるなら/ 無料で転職サポートを受ける 経理の志望動機の作成方法 経理経験者の志望動機のポイントとしては、「何の業務をどこまでできるかを明確にする」「転職先で活かせることや新たに挑戦したい仕事を明確にする」の2点を意識しましょう。 何の業務をどこまでできるかを明確にする まずは、どのような経理業務に携わってきたかを具体的に説明します。 たとえば、日常の帳簿管理や決算業務、税務申告などです。 経理業務は組織体制や企業規模によって、担当者1人が対応する業務範囲が異なります。 こうした部分も考慮し、わかりやすく説明できるのが理想です。 転職先で活かせることや新たに挑戦したい仕事を明確にする 転職先で活かせることに関しては、これまでの経験を新しい職場でどのように活かせるかを具体的に示します。 たとえば、「過去に効率化やコスト削減に貢献した経験を挙げ、それを新しい職場でも実現したい」などです。 新たな挑戦への意欲の表明も重要です。 新しい環境で学びたいことや、専門性を深めたい分野を明確に説明しましょう。 また、その新たな挑戦が、長期的なキャリアプランとどのように結びついているかを説明することも重要です。応募先企業での長期的なキャリア構築への意欲を示せるため、プラスの評価につながりやすくなります。 転職理由の具体的な例文は以下の記事でご紹介しています。 あわせて読みたい 経理の職務経歴書の書き方は?ポイントや必ず記載するべき内容など 経理の志望動機【例文付】未経験者・経験者向けNG例・OK例を徹底解説 \求人紹介から選考対策も!/ 無料の転職サポートを受ける 転職前に考えておくべき経理のキャリア 経理の転職では、求人探しなどの転職活動を始める前に、経理のキャリアについて深く考えておきましょう。 特に、書類選考や面接で志望動機を伝える際には、将来のキャリアを明確にすることで、自分が進みたい方向性を具体的に示すことができます。 経理の王道キャリアプラン4選 経理の王道キャリアプランには、以下の4つがあります。 ・経営に携わる上位職を目指す ・中小企業から大企業の経理へ転職する ・資格を取得し独立開業する ・外資系企業に転職 目指すキャリアプランによって、必要となるスキルや経験は異なります。 そのため、早い段階で自分が進みたい方向性を描き、計画を立てておくことが大切です。 また、キャリアプランに「正解」はありません。 自分の価値観や目標に基づいた方向性を考え、実現するための具体的な方法をキャリアアドバイザーに相談するのも良い手段です。 キャリアプランを考える際の落とし穴 経理としてキャリアプランを描く際には、注意すべきポイントがいくつかあります。 全て予定通りにいくとは考えない 理想が高すぎるキャリアプランは、現実とのギャップを埋めるのが難しくなる場合があります。 必要に応じて柔軟に見直すこともキャリアプランを考える上で重要です。 また、身近な上司や先輩をロールモデルとして参考にすると、現実的な目標を設定しやすくなります。 経理からのキャリアチェンジも視野に入れる 経理のキャリアプランといっても、「最終的なゴールが経理でなければならない」と考える必要はありません。 特に経理は経営に関わる数値を扱うため、経営企画や会計系コンサルタントなど、他分野へのキャリアも視野に入ておくとよいでしょう。 \キャリアの可能性が広がる!/ 転職のプロにキャリア相談をする 経理の転職理由 この章では、「経理のよくある転職理由」と「面接で評価される転職理由の伝え方」について見ていきましょう。 経理のよくある転職理由 2023年1月~12月の1年間で、MS-Japanに登録いただいた経理・財務の転職希望者を対象に独自調査を行った結果、以下のような結果になりました。 最も多かった理由が「スキルアップ」の41.3%でした。経理は1年間の業務の流れがおおよそ決まっているため、何年も同じ職場にいると、どうしても成長の鈍化を感じてしまいがちです。転職によって新しい業務にチャレンジして、スキルアップしていきたいという方はやはり多いことがわかります。 また、「会社の将来性不安」や「年収アップ」も20%前後と、約5人に1人が転職理由として挙げていることがわかります。 経理の仕事は売り上げに直結しないため、評価に繋がりにくく、他の部署に比べて昇給昇格が遅い、またはある水準で年収が頭打ちになってしまうという企業もあります。 また、「会社の将来を考えるとこれ以上の年収アップは期待できない」と、会社の将来性に不安を感じ、転職決意する方も少なくありません。 ▶詳しくはコチラ:経理でよくある転職理由は?転職活動で損をしない伝え方を解説! 面接で評価される転職理由の伝え方 「人間関係」「スキルアップ」「年収アップ」等、経理担当者が転職を考える理由は人それぞれですが、応募先企業への伝え方に悩む方は多いでしょう。 前向きな転職であれば、ありのままの転職理由を伝えれば問題ありませんが、職場環境や待遇面が転職理由の場合、前職での不満をそのまま採用担当者に伝えることは好ましくありません。 その一方で、矛盾するようですが、前向きな内容のみの転職理由は、実はあまり印象がよくないこともあります。 本音の部分の不満を隠しすぎて、前向きなことのみしか語らない場合 、本心が見えづらい為、伝え方には注意が必要です。 転職理由を伝えるときは、本音を隠しすぎずかつ前向きな理由を加えて伝えることがポイントとなります。 例えば残業を減らしたいのであれば、「残業を減らして資格の勉強をしたいと考えている」「子どもが生まれたので、子どもとの時間が取れる仕事に就きたい」などの、具体的な理由を伝えると本心から話している印象になり、心象が良くなりやすいと言えるでしょう。 以下の記事では例文付きで経理の転職理由の伝え方を解説していますので、転職理由の伝え方に悩んでいる方は参考にしてみてください。 あわせて読みたい 【経理の転職理由】好印象な伝え方や例文、転職成功事例など \経理・財務特化の転職エージェント!/ MS-Japanに無料会員登録する 経理の面接でよく聞かれる質問と注意すべきポイント 経理は、経験業務・知識によって担当業務が異なるため、何の業務をどこまで経験しているのかを具体的に伝える必要があります。 面接準備の際には、これまでに経験した職務内容や実績などを詳細に洗い出す「キャリアの棚卸」を行いましょう。 「キャリアの棚卸」では、実績だけを洗い出すのではなく、自分が携わった業務でどんな役割を担ったか、気をつけたことは何か、それによってどのような結果が得られたかなど、過程を中心に振り返ることがポイントです。 一般的に経理の求人は、実務を担う一般職と幹部候補・管理職候補の二通りです。 一般職では、経験業務によって担当業務の振り分けが決定されます。そのため、具体的な業務内容をしっかりと伝えることが重要です。 幹部候補・管理職候補の場合は、マネジメント経験が重視されますが、何名規模の部門でどのようなマネジメント業務を経験していたのかを詳細に伝えましょう。 あわせて読みたい 【経理の面接でよくある質問集】逆質問で聞くべきことや注意点など \求人紹介から選考対策も!/ 無料の転職サポートを受ける 経理の転職で求められるスキル・知識 この章では、経理の転職で特に求められる3つのスキルと知識を紹介します。 「簿記」に関する知識 経理の基本的な考え方や仕訳を理解する上で、「簿記」に関する知識は必須です。 特に日商簿記2級は、経理スタッフとして必要な簿記知識を証明する資格として、多くの求人で募集要項に記載されています。 「簿記」の知識をアピールする上で、取得しておくと非常に有効な資格と言えるでしょう。 ITスキル 近年では、会計ソフトやクラウドサービスを活用することが経理業務の一般的なスタイルとなっています。 これらのツールを効率的に使いこなすためのITスキルは、転職市場で求められるスキルの一つです。 さらに、AI技術を活用して経理業務の効率化を図る動きも進んでおり、AIを適切に活用できる能力も、経理担当者にとって重要な力量と見なされます。 そのため、ITスキルの向上は転職活動でアピールポイントとなるでしょう。 コミュニケーションスキル 経理の仕事は単に数字を扱うだけではありません。 関係部署や経営陣に対して、財務報告や予算案を説明する必要があるため、優れたコミュニケーションスキルが求められます。 特に、予算案を提案する際には、相手を納得させるための説得力が重要です。 ただ一方的に自分の意見を押し付けるのではなく、相手の立場を理解した上で話し合う能力が求められます。 あわせて読みたい 経理の転職で求められる実務経験とは?経験が浅い場合は何をアピールすればいい? 簿記とは?日商簿記1~3級の合格率や勉強時間、合格後のキャリアなど \まだ、キャリアの可能性が見えないかも/ キャリアプランを提案してもらう 経理の転職で有利な資格5選 スキルや知識を客観的に証明する意味で、資格の取得も転職で武器になります。 経理に役立つ資格は20以上ありますが、中でも転職に役立つ資格を5つ紹介します。 日商簿記2級 日商簿記2級は、経理職における基本中の基本ともいえる資格です。 企業会計に関する基礎的な知識や、仕訳・試算表・精算表の作成、工業簿記の理解など、実務に直結する内容が問われます。 合格率は20~30%前後と一定の難易度がありますが、独学でも十分に対応可能です。比較的取得しやすい資格といえるでしょう。 経理職の採用条件や「歓迎資格」として最もよく挙げられるのがこの日商簿記2級です。 資格取得によって「経理の基礎が身についている」と判断され、未経験者であっても書類選考を通過しやすくなります。 仕訳入力や月次・年次決算の補助など、日常的な経理実務に広く役立つ知識を身につけられる点も魅力です。 あわせて読みたい 【日商簿記2級の合格率と推移】2025年最新情報やネット試験との比較など ビジネス会計検定 ビジネス会計検定は、財務諸表を「読む」「分析する」力を問う検定で、大阪商工会議所が主催しています。 簿記が「作る力」に焦点を当てた資格であるのに対し、ビジネス会計検定は「読み解く力」に特化しています。 そのため、経営層や他部門とのコミュニケーションを求められる場面でも活躍できるでしょう。 2級の合格率は40〜60%と比較的高く、初学者にも取り組みやすい資格です。 ビジネス会計検定を取得することで、財務分析や経営状況の把握ができる能力があることをアピールできます。 特に、管理会計や経営企画との連携を行う際に役立ちます。 また、年次決算だけでなく、予算実績管理や経営資料の作成といった業務にも知識を応用することが可能です。 あわせて読みたい ビジネス会計検定は役に立たないって本当?難易度や簿記との違いなどを解説 FASS検定 FASS検定は、経済産業省が監修する実務能力評価試験で、経理・財務の4つの分野(資産、決算、税務、資金)におけるスキルを可視化できる点が特徴です。スコアはA~Eランクで評価され、合否はありません。 FASS検定は特に、経理業務のどこに強みがあるのかを客観的に証明できる点が評価されます。 職務経歴が浅い人でも「実務対応力」を可視化できるため、実践力重視の企業や大手企業では有利に働くこともあります。 具体的には、売掛金・買掛金管理、原価計算、決算業務、資金繰りといった業務で学んだ内容を直接活かせるでしょう。 あわせて読みたい FASS検定は意味ない?経理の転職で役に立つ?レベル別求人例など 公認会計士 公認会計士は国家資格のひとつであり、監査・会計・財務の専門家として知られています。 試験は短答式・論文式と高度な内容で構成されており、合格率が10%を下回ることもある難関資格です。 また、資格取得には2〜3年の学習期間が必要とされ、実務補習や実務経験も要件に含まれます。 公認会計士の有資格者や試験合格者は、経理部門においても特に「高度な専門性を有する人材」として扱われます。 連結決算や開示書類の作成、IFRS対応、内部統制整備など、上場企業・外資系企業のハイクラスポジションで重宝されるほか、経営層に近い立場としてCFO候補に抜擢されるケースもあります。 あわせて読みたい 【公認会計士の転職】完全ガイド|おすすめの転職先17選や年収相場、年代別転職のポイントなど 税理士・税理士科目合格 税理士は、法人税や消費税、相続税など、「税務」に特化した国家資格です。試験では全11科目中5科目に合格する必要があり、合格率は各科目10〜20%前後とされます。ただし、科目合格制度があり、1〜2科目だけの合格でも転職時に評価される場合があります。 経理実務においては、特に決算期の法人税・消費税の申告業務、税務調査対応、税務レビューなどにこの資格が役立ちます。また、税効果会計など専門的な会計処理が必要な業務にも強みを発揮できます。 税理士試験科目の合格者は「税務会計のプロ」として即戦力採用されることも多く、特に決算対応・税務申告に力を入れている企業では高く評価されるでしょう。 あわせて読みたい 税理士の転職|プロの視点で解説!年収や年齢問題など【MS-Japanアドバイザー監修】 税理士科目合格は1科目でも転職市場価値が高い!転職先や特に評価されやすい科目は? \あなたの資格、活かしきれてないかも/ 資格を活かせる求人を紹介してもらう 【年代別】経理転職のポイント この章では、年代別に経理の転職のポイントをご紹介します。 【20代】経理転職のポイント 20代の場合、経理経験がすでにある方もいれば、他業種から第二新卒やキャリアチェンジで経理を目指す人もいるでしょう。 以下に、経理経験者、未経験者に分けて転職のポイントをご紹介します。 20代経理経験者の場合 コロナ禍から徐々に経済が回復し、企業の業績が向上しているため、経理職を求める企業が増えている一方で、人口減少や少子高齢化により、働き手としての人材は不足しています。 特に20代で経理経験を持つ人材が少ないため、多くの企業で経理部門は若手人材が足りていない状況です。 経理業務ではビッグデータやAI技術を駆使した自動化が進みつつあるため、ITスキル・リテラシーが必要とされるようになり、デジタル領域に強い若手の需要が高まっています。 20代の経理経験者が転職する際には、ITパスポートなどのIT関連の資格を取得するなど、IT関連の知識を身に着けておくと、転職時に有利に働きます。 20代経理未経験者の場合 経理の求人では経験やスキルが重視されるため、未経験者や第二新卒者よりも経験者が優遇されることは事実です。しかし、未経験・第二新卒でも応募できる求人は一定数存在します。 経理の実務経験がない、もしくは少ない場合は、簿記や税務の資格を取得して知識レベルを示すことができます。20代の場合は、簿記2級以上の資格が転職活動に役立ちます。 簿記2級は、経理業務における基礎的な知識を身につけることができる資格で、応募条件として簿記2級必須条件にしている求人も多く見受けられます。 未経験から経理への転職を目指す場合、まずは簿記2級を取得しましょう。 あわせて読みたい 20代未経験で経理に転職!転職事例やアピールポイント、求人例などを紹介 【30代】経理転職のポイント 経理の転職における30代は、即戦力スキルが求められます。20代であれば、第二新卒としてポテンシャル採用されるケースもありますが、30代になると、経験値や実務スキルが評価ポイントとなります。 そのため、主な経理経験やスキルを棚卸しして、応募先企業でどのように貢献できるか具体的に伝えることが重要です。 主に求められるスキルとしては、以下が挙げられます。 経理スキル 経理関連業務のスキルは大きく以下のように分類されます。 ・主計 …単体の決算や連結決算 ・財務 …資金繰りやデットファイナンス、エクイティファイナンス ・税務 …法人税などの申告 ・管理会計 …予算や費用・収益などについての分析 30代であれば、決算業務の経験があれば十分に転職が可能でしょう。 加えて、財務、税務、管理会計などの経験がある場合はプラス評価になるため、転職時のアピールポイントになります。 コミュニケーションスキル 経理業務がシステム化されている近年は、単純作業がシステムに置き換えられ、上流工程の経理スキルを持つ人材のニーズが高まっている傾向です。 例えば、現場から届く取引の記録を見て、「今どんな取引を行っているのか」 「経理上どんなことが問題となり得るのか」 を推測し、現場にアドバイスできる人材が評価されるでしょう。 現場から相談を受けた場合に「○○だからダメ」と単に答えるのではなく、 「〇〇だからダメですが、△△ならできるかもしれません。クライアントとは□□と交渉してみてはどうでしょう?」 などのアドバイスができるコミュニケーションスキルが求められます。 マネジメントスキル 30代後半に近づいてくると経理職においてもマネジメントスキルが求められるケースが多くなります。 管理職経験があれば、多くの企業において強いアピールポイントになります。しかし、管理職経験はなくても、例えば プロジェクトチームのリーダーとして部下や後輩の指導・評価を行った経験などは大きな評価の対象になります。また、システムの新規導入を担当するなど業務改善・プロジェクトマネジメントを行った経験も、マネジメントスキルの一つとして評価されます。 あわせて読みたい 30代経理の転職で求められるスキルは?転職のポイントを解説! 【40代】経理転職のポイント 40代の経理人材が転職する際のポイントとしては、転職活動期間を長めに見込んでおくことが重要です。 企業が20代、30代の採用を検討する際、任せたい業務経験が十分でなくてもポテンシャルを見込んで採用オファーを出すケースも少なくありません。 しかし、40代を採用する場合、採用企業側は応募者の経験業務と任せたい業務内容を勘案し、即戦力で活躍してくれる人材を求める傾向が強くなります。 40代の場合は経験業務と採用側のニーズのマッチングがより細かくなってくるため、双方の希望条件が合致する企業・求人を探すこと自体に時間を要する可能性が高くなります。 転職活動時は初めから短期で決めようとせず、数か月スパンでの転職活動になる可能性を念頭に置いておきましょう。 また40代の場合、経理の実務経験が求められることはもちろん、課長職・部長職といった役職に就く年代に差し掛かるため、実務経験以外にもビジネスマンとしてのスキルも求められます。 主に求められるスキルとしては、以下が挙げられます。 経理業務経験 40代の経理人材は、即戦力として経理業務の経験を求められます。具体的には、日次業務はもちろん、月次・年次の決算業務までの経験を有していることが望ましいでしょう。 マネジメントスキル(素質) 40代になるとマネジメント経験、もしくは管理職・マネージャーとしての素質も求められるようになります。 マネジメント経験がある場合は、経験した内容を具体的に話す準備をしましょう。経験年数や部下の人数、プロジェクト管理や教育・研修の経験などを具体的に言語化しておくことが重要です。 柔軟性 40代には転職先の会社の風土やルールに対応できる柔軟性も重要です。 選考時には、部署移動の経験や、新しいことに積極的に挑戦した経験など、柔軟性をアピールできるエピソードを用意しておくことをおすすめします。 あわせて読みたい 【40代経理の転職】転職市場や平均年収、転職時のポイントなど<転職事例あり> 【50代】経理転職のポイント 近年の転職市場では、50代の経理求人は増加傾向にあります。60代でも働いているのが当たり前となった昨今、50代での転職はより身近なものになったと言えるでしょう。 経理はここ数年高い求人倍率をキープしており、採用意欲が高い企業では50代の人材採用も積極的に行っています。 また、経験したことのある業務が幅広いほど即戦力として評価されやすいため、50代の経理人材は十分に転職が可能です。50代の経理人材が転職する際に押さえるべきポイントは以下の通りです。 事前の情報収集を念入りに 年収や業務内容はもちろんですが、経理部門のメンバー構成・年齢構成についても調べておくことが重要です。 転職先で上司が年下になる場合もあるため、上司となる方の性格などの情報も知っておくと、入社後ミスマッチとなるリスクを減らせます。 しかし、一般的な転職サイトでは求人票に記載されていない限り、自力で調査するのは難しいでしょう。 転職エージェントであれば、企業の内情に詳しいキャリアアドバイザーから、メンバー構成などの詳細情報を事前に把握することが可能です。 現職と同等のポジション・年収に固執しない 採用する企業側の立場からすると、どれだけの実績があって現在の年収が高くても、転職直後から同等の活躍が保証されているわけではないため、必ずしも現職と同じ待遇で転職できるとは限りません。 50代の転職では、現職のポジションや年収にこだわるよりも、自身の経験値やスキルとマッチする企業を選ぶことが重要です。 転職後の活躍を評価されれば、現職のポジションや年収に追いつくことも十分可能です。 一時的な収入や肩書きのダウンはある程度受け入れる心構えでいるほうが、結果的には満足度の高い転職が実現できることもあります。 あわせて読みたい 経理は50代でも転職できる?注意点や経験者・未経験者別転職成功の秘訣など \経理・財務特化の転職エージェント!/ MS-Japanに無料会員登録する 【企業規模・フェーズ別】経理の転職のポイント この章では企業規模・企業フェーズ別に経理の転職のポイントをご紹介します。 大手企業の経理 大手企業に経理として転職する場合は、以下の3点が主なポイントになります。 専門性が重視される 大手企業では、経理業務を業務分野ごとに担当分けしていることが一般的なため、採用にあたっても各分野の専門性が重視されます。 経理の専門分野は大きく分けると、以下の4つに分類できます。 ・主計 …単体あるいは連結での決算 ・税務 …税務申告 ・財務 …資金繰りや借り入れなど ・管理会計 …予算と結果、費用と利益などの分析 上記のうち、いずれかの業務に強みを持っていると、大手企業への転職可能性が高まるため、実務経験を通じて業務スキルを高めたり、自己研鑽として税法の学習をするなど、自分の得意分野はこれだと言える強みを持っておくことがポイントです。 マネジメント経験も高評価 大手企業では、チームリーダー経験などのマネジメント経験も高評価となります。 人員が多く、業務が細分化されているため、中小企業よりも経理部門におけるマネジメントポジションの数が多い傾向ためです。 すでにマネジメント経験をお持ちの方は、転職時に積極的にアピールしていきましょう。 英語力や国際会計の知識 近年では日系企業も、海外進出するケースが多いため、大手企業への転職では、英語力や国際会計の知識についても問われることがあります。 実際の海外取引経験がなくても、USCPA(米国公認会計士)などの国際会計基準の資格や語学力がある場合には評価されます。 TOEICのスコアでは700点程度が一つの目安になりますが、800点以上のスコアを保有していれば、さらに転職時に有利になるでしょう。 IPO準備企業の経理 IPO準備企業に転職する場合、実務経験ももちろん評価ポイントになりますが、IPO準備企業ならではの選考ポイントがあります。 具体的には、以下の2つのスキルは、どのIPO準備企業でも重視されるでしょう。 チャレンジ精神 IPO準備企業では、開示体制を整えるために財務諸表を新たに作り直したり、経理規定の見直し、決算の早期化、プロセス設計、API連携といった業務フローの整備など、ルーチン業務だけでなく、新たなものを作り出す、既存の規定やフローを整備するといった業務が多くなります。 そのため、「0→1にした経験や、新しいことにチャレンジする姿勢を持った人材」を採用企業は評価します。 現職・前職などで部署異動した経験、会計システム導入などの新しいものを取り入れる業務に挑戦した経験がある方は、強いアピールポイントになるでしょう。 尚、必ずしも業務上の経験である必要はありません。プライベートで、大人になってから新しく始めた趣味の話など、チャレンジングな性格を示せるエピソードがあれば、面接時に話せるように整理しておくといいでしょう。 コミュニケーション力・交渉力 IPO準備企業では監査法人への対応、証券会社と証券取引所による審査対応といった対外的な対応も多く発生します。その企業の組織構成や転職時の役職にもよりますが、経理の担当者・責任者として会社を代表して対応するケースも想定されるため、対外的なコミュニケーション力や交渉力はIPO準備企業に転職するのであれば必須といえます。 また、IPOを達成するためには経理体制の強化だけでなく、管理部門全体、ひいては全社で上場に耐えうる強固な組織づくりをしていく必要があるため、対外的なコミュニケーション力や交渉力のみでなく、社内での調整力や協調力も必要となります。 選考時には現職・前職での対外交渉経験や、社内の他部署と協力して業務を進めた経験などをアピールすると、高評価につながるでしょう。 あわせて読みたい IPO準備企業における経理の役割・転職メリット・キャリアパスを紹介! 中小企業の経理 中小企業の経理業務は日常業務、月次業務、年次業務の3つに分けられます。 ・日常業務:現金出納管理、伝票管理、会計帳簿の記帳、仕入・売上の管理、請求書の発行、入金確認、預金管理など ・月次業務:経費精算、月次決算、給与計算、税金や保険料の計算・納付など ・年次業務:年次決算、年末調整、税金計算と納付、償却資産の申告、棚卸など 中小企業の経理業務の特徴は、1人の経理担当者が上記の業務について幅広く対応している点です。場合によっては経理以外の人事・総務業務まで幅広く担当するケースもあります。 また、どの業務を会計事務所や社会保険労務士などにアウトソーシングしているのかによって、担当しなければならない業務範囲が異なってくるため、中小企業同士においても経理業務の内容は違ってきます。 上記のように幅広い業務を担当するケースが多いため、中小企業は応募者にスペシャリスト気質であることよりも、ゼネラリストであることを求めます。そのため、転職活動の際には、幅広い業務に挑戦したいという、前向きな意欲を示せると高評価でしょう。 中小企業への転職はキャリアダウンになるのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。 大手企業などと違って、役職者のポストに空きがあることが多く、また、年功序列ではなく成果主義で出世していけるケースもあるため、大手企業からあえて中小企業に転職する方もある程度います。 さらに、やりがいという面においても、中小企業であれば資金調達、資金繰りや 経営企画室の業務である、予算の作成や中期経営計画の作成など、レベルの高い業務に携われる機会も増えます。会社経営全体を見ながら経理業務に関与できる点は、中小企業ならではのメリットといえるでしょう。 あわせて読みたい 中小企業の経理とは?大企業との違いやメリット、転職のポイントなど ベンチャー企業の経理 ベンチャー企業は組織として成熟していない会社も多く、特に経理などの管理部門の整備は後回しとなってしまいがちです。 経理担当者がベンチャー企業で担当する業務範囲が幅広いものとなり、人事、総務、法務などの見識や役割、具体的な業務が求められることもあります。 しかし、考え方によっては今後のキャリア形成を考えた場合、大きなチャンスであるともいえるでしょう。縦割りになりがちな管理部門の中で、広範囲の業務に携わることはスキルの幅を大きく広げていくことができるためです。 このことは、将来、経理を軸として管理職や経営幹部を目指すのであれば、必要不可欠です。 ベンチャー企業の経理に転職を希望する場合には、転職エージェントのサポートを受けながら転職活動を進めていくのがおすすめです。 ベンチャー企業は数多くあり、それらの内部は企業の数だけ異なりますので、実情はWebなどで収集できる情報だけでは把握できないでしょう。 しかし、転職エージェントであれば顧客であるベンチャー企業と日ごろから連絡を取っており、経理担当者に求める役割についても情報収集していますので、入社してから“こんなはずじゃなかった……”といった状況を避けることができます。 あわせて読みたい ベンチャー企業の経理はどんな仕事?魅力や向いている人、転職成功の秘訣など \まだ、キャリアの可能性が見えないかも/ キャリアプランを提案してもらう 経理経験者の転職成功事例 この章では、経理経験者の転職成功事例を紹介します。 非上場企業から上場企業への転職成功事例 Aさん(30代/男性) 転職前:非上場企業 経理 転職後:上場子会社 経理 年収100万円アップ 資格:簿記2級 Aさんは、7年半非上場企業で経理担当して、日次業務から年次業務まで幅広い経理経験を積んでおり、これらの経験を活かしてさらにスキルアップしたいと考え、転職活動を始めました。 転職活動では、キャリアの棚卸と今後のキャリアプランをキャリアアドバイザーと一緒に考え、選考に向けて十分な準備を行いました。 結果、経験を活かせる上場子会社の経理として転職決定し、100万円の年収アップもじつげんすることができました。 柔軟な働き方を目指した転職成功事例 Kさん 30代前半/女性 転職前:上場グループの事業会社 経理 転職後:非上場の事業会社 経理 年収30万円アップ 資格:日商簿記2級 Kさんは、在籍していた会社の経理部門で産休育休を経て職場復帰し、フルタイム勤務をされていました。 しかし、徐々に任される仕事量が増えていき、仕事と育児の両立に難しさを感じ、転職を決意されました。 転職活動では、柔軟な働き方と少ない残業という2つの希望条件をもとに求人を探していたため求人の数が絞られました。 ただ、産休育休前に主体的に業務に取り組んでこられ、一連の経理業務経験があることを評価され、最終的には2つの希望条件に加え、30万円の年収アップを実現できる企業に転職決定しました。 \転職しないは"機会損失"です!/ 無料の転職サポートを受ける 経理の仕事内容 この章では、経理の仕事内容について簡単に解説します。 特に未経験から経理への転職を希望している方は、選考に進む前に経理の具体的な仕事内容を把握しておきましょう。 経理の日次・月次・年次業務 経理の仕事を期間単位で分けると、「日次業務」「月次業務」「年次業務」の3つに分けることができます。 それぞれの具体的な業務は、以下の表をご確認ください。 業務分類 具体的な仕事内容 日次業務 ・現金預金管理・伝票処理・経費精算 など 月次業務 ・買掛金・売掛金の管理・給与計算・社会保険料納付 など 年次業務 ・年末調整・決算書・確定申告・税金の納付 など これらの業務は企業規模や組織の構造によって異なりますが、正確さや効率性が求められる点は共通しています。 経理と会計・財務の違い 経理の仕事をより深く理解するためには、経理に似ている職種である「会計」「財務」との違いを把握することが大切です。 経理と会計の違い 会計は、企業の経済活動を記録し、それをもとに経営者や株主などに財務情報を提供する役割を担います。 一方、経理は取引の記録や管理、決算書作成までを担当します。会計全体の一部を構成する業務が経理といえるでしょう。 経理と財務の違い 財務は、企業が成長するために必要な資金を調達・運用する業務です。 銀行融資や資金調達、予算編成、M&A戦略などが含まれます。 経理は財務活動を支える基盤として、帳簿データや決算情報を提供します。 両者は密接な関係にあるものの、役割は明確に異なります。 \経理・財務特化の転職エージェント!/ MS-Japanに無料会員登録する 未経験者の経理転職は難しい?未経験転職のポイント 経験者であっても経理の転職は容易ではありませんが、未経験者の転職はさらに難易度が上がります。 この章では、未経験から経理へ転職するポイントを解説します。 日商簿記2級を取得する 未経験から経理を目指す場合、日商簿記2級は必須の資格と言っても過言ではありません。 日商簿記2級を取得していることで、「簿記や財務諸表についての基礎知識がある」ことを証明できます。 実際にMS-Japanを利用して経理への転職を決定した方のうち、約73%の方が日商簿記2級を保有していました。 あわせて読みたい 簿記2級で経理や会計事務所に転職できる?未経験から採用されるコツを解説 経理関連の業務経験を洗い出す 経理としての実務経験がない場合でも、経理に関連する業務経験があれば、それをアピールすることが重要です。 経理の仕事に直接関係がない場合でも、数値をもとにした分析業務やお金に関わる業務の経験がないか洗い出しましょう。 特に経理に親和性の高い業種や職種に関しては、次に章で解説します。 20代のうちに転職活動を始める 未経験から経理を目指す場合、20代のうちに転職活動を始めることが転職成功への近道です。 年齢が上がるにつれて、求められるスキルや経験のハードルが高くなるため、30代以上で未経験の場合、ポテンシャルだけでスキルや経験の不足を補うのは難しくなります。 20代の若さを武器に、学習意欲や柔軟性をアピールしつつ、転職活動を進めましょう。 \経理・財務特化の転職エージェント!/ MS-Japanに無料会員登録する 経理に親和性のある業種・職種からの転職 経理の業務に親和性のある税理士補助や銀行から経理へ転職を検討する方も多いです。ここでは、それぞれの転職のポイントを見ていきましょう。 税理士補助から経理 経理職と言っても業務は多岐に渡りますが、特に税務や会計業務で企業が求人を出している場合、税理士補助経験は選考において有利にはたらきます。 税理士補助の経験が豊富な方なら、即戦力として活躍が期待できるので、積極的に採用したいと考える企業は多いです。 しかし、一口に税理士補助経験と言ってもさまざまです。 転職活動をするなら、税理士補助の経験の棚卸しをしておきましょう。 勤務していた税理士法人や会計事務所などの規模、担当していた業務内容、得意としている仕事などの整理をしておくと、ご自身の経験を活かせる企業を見つけやすく、転職活動をスムーズに進めることができます。 銀行から経理 銀行員はスキルの面で経理とかみ合いが良い傾向にあります。 銀行員は経理畑を歩んでいる人に比べて、会社組織が必要とする知識を横断的に手にする機会に恵まれているため、財務・法務・税務といった面でも役に立つ「管理部門の何でも屋」的ポジションを狙うというアプローチもあります。 小規模な中小企業であれば、経理部門≒管理部門的な立ち位置で仕事を進めることも珍しくありません。 求人情報を熟読し、自分でも活躍できる立ち位置での採用かどうかを見極めた上で、転職を検討しましょう。 あわせて読みたい 銀行員から経理を目指すには?転職を成功させるポイント 営業から経理 結論から言えば、営業から経理へ転職することは十分可能です。 但し、幾つかの条件をクリアする必要があり、簡単な転職ではありません。 そのため、安易に転職活動を始めることは危険です。転職可能性があるのか否かをしっかりと見極めて、転職活動に取り組む必要があります。 まず、未経験での転職ということになるので、日商簿記検定2級は取得しておきましょう。また、キャリアチェンジになるため、年齢は30歳前後までが目安です。 営業職では売上や利益などの「数字」を意識して働くことが多く、数字を管理する点で経理職と通じる部分があります。 自分自身が、計数管理が得意だったり、自社や顧客の決算資料を読み込んだりして、営業活動に活かしているという方は、経理の適性があるかもしれません。 経理においては以下のようなスキルが求められます。 ・正確な事務処理能力 ・コミュニケーションスキル ・会計や経営の知識 上記の他に、大前提として、エクセルを中心としたパソコンスキルがあることが求められます。入社後にその会社が使用する会計ソフトの操作を学ぶことになりますが、会計処理がどのようになされるかの前提として、計算の仕組みが想像できることは必須でしょう。 経理に未経験から転職する際のコツと注意点ですが、転職理由をネガティブに伝えないようにすることが大切です。 「ノルマがキツイ」「ワークライフバランスがとれない」といった理由が多いかもしれませんが、それらをそのまま伝えるのは得策ではありません。 どの仕事もつらい場面は存在するので、「営業よりも経理の方が楽だ」と誤解していると思われる可能性があります。 あくまでも経理の仕事に挑戦したかった旨を第一に伝えましょう。 あわせて読みたい 営業から経理へ転職はできるのか?キャリアチェンジの注意点やコツ \転職に不安があるなら/ 無料で転職サポートを受ける リモートワーク可の経理に転職する方法 経理業務は、完全に在宅勤務へ移行するのが難しい業務のひとつです。 会社のお金や取引の流れを記録する経理部門では、伝票の書き起こしや請求書の発行、書類の捺印など、オフィスへの出社が必要な業務が多くを占めるため、在宅勤務のハードルが高くなっています。 しかし、書類・印鑑の電子化やセキュリティ構築が進んでいるITに強い企業であれば、経理でも在宅勤務可能と言えるでしょう。 弊社MS-Japanが実施した「【2023年版】管理部門・士業のリモートワーク求人の動向を徹底解説」では、リモートワーク可能な求人を掲載している企業を業種で分類すると、27.3%が「IT・通信全般」でした。 経理で在宅勤務を希望する方は、IT系企業の経理への転職を検討してみてはいかがでしょうか。 また、在宅勤務の経理へ転職成功させるには、求人が多い時期を選ぶことも1つのポイントです。 日本は3月末決算の企業が多いため、税務申告期限は5月末で、4~5月が決算業務に追われる繁忙期に該当します。 そのため、企業が経理の求人を出すタイミングは、繁忙期の2~3か月前の1~2月あたりに求人募集を始める企業が多くなります。 もちろん1年を通してどの時期でも転職できますが、求人案件が多い時期を狙ったほうが、より希望に添った転職先を見つける確率が高まるでしょう。 あわせて読みたい 経理は在宅勤務が難しい?在宅勤務できる企業の特徴や求人例 求人特集リモート可の経理求人を探す 経理の将来性 AI時代に備えるために・・・ 「将来なくなる仕事」の中に経理職がランクインするなど、経理の将来性を考える方も増えています。 経理の将来性はその人材が持つスキルによって「ある」とも「ない」とも言えます。 将来的に定型的な業務を担うスタッフのニーズは減少する可能性がある一方で、数値を分析し経営判断に活かせる人材や、M&Aなど専門性の高い業務に対応できる人材は、今後も重要な存在として求められるでしょう。 経理職における定型業務が、AIに取って代わられる時代がもうすぐそこまで来ている中で、将来、経理職が生き残っていくためには、「経理の専門知識を高める」だけでは厳しい時代になってくると予想されます。 会計・税務における影響をデータから読み取って経営のアドバイスができる戦略立案力や判断力を培っていき、来るべきAI時代に備えていきましょう。 あわせて読みたい 経理の仕事はなくなる?経理の将来性ってどうなの?【現役キャリアアドバイザー監修】 \同期はもう転職活動を始めてるかも/ 今すぐ転職活動を始める まとめ:経理の転職には「転職エージェント」がオススメ! 経理の転職は、経験者であっても未経験者であっても難易度が高く、成功させるためには十分な準備と対策が必要です。 特に、転職活動を始める前にキャリアプランを明確にし、目指す方向性を具体的に描いた上で、それに基づいたスキルや資格の取得、これまでの経験を効果的にアピールすることが求められます。 「MS-Japan」は、管理部門に特化した転職エージェントとして、業界最大級の求人数を誇り、経理の転職市場についても豊富な知識と経験を有しています。 求職者一人ひとりの状況に合わせた求人紹介や選考対策、キャリアプランニングなどを通じて、転職活動をサポートします。 経理の転職を成功させ、理想のキャリアを実現するために、ぜひ「MS-Japan」をご利用ください。
-

会計事務所から経理への転職は難しい?事前準備や志望動機・自己PR、成功事例など
近年、会計事務所から事業会社の経理への転職を目指す人が増えています。 この記事では、会計・税務領域を専門とする現役キャリアアドバイザーが監修して、会計事務所から経理への転職について解説します。 自己PR・志望動機の注意点から会計事務所経験者を歓迎する求人、転職成功事例も紹介するので、ぜひご自身の転職活動やキャリアプランニングの参考にしてください。 記事の要約 ●会計事務所と経理では業務内容やキャリアパスが大きく異なるものの、会計事務所での経験は経理でも即戦力として評価されやすい。 ●志望動機は「経理を志望した理由」と「応募先企業を志望した理由」を分けて考えることが重要。 ●会計事務所から経理への転職を目指すなら、今すぐ【転職相談はこちら】へ。 「会計事務所から経理に転職は難しい?」現役キャリアアドバイザーが解説 会計事務所と事業会社の経理では多くの違いがあるため、「転職は難しいのでは?」と感じる方も多いでしょう。 しかし、会計事務所から経理への転職は一般的な選択肢です。 会計事務所で得た知識・スキルは、事業会社の経理で即戦力として評価されるでしょう。 弊社MS-Japanでも、「会計事務所経験者歓迎」の経理求人を多く取り扱っています。 また、実際に会計事務所から経理への転職を成功させた方も多数いらっしゃいます。 ただし、会計事務所と事業会社では事業形態が異なるため、未経験からのキャリアチェンジとみなされた場合、20代の方が採用されやすい傾向があります。 30~40代であっても、移転価格や連結納税、タックスヘイブン税制など高度な税務経験があれば、事業会社から高く評価されるでしょう。 \経理・財務特化の転職エージェント!/ MS-Japanに無料会員登録する 会計事務所と経理を比較 会計事務所と事業会社の経理では、具体的に何が異なるのでしょうか。 ここでは、業務内容・福利厚生・キャリアパスを比較して解説します。 会計事務所 事業会社の経理 業務内容 クライアントの経理・税務業務を代行する 【税理士】・税務代理・税務書類作成・税務相談など 【事務スタッフ】・記帳(経理事務)代行・巡回監査など 自社の経理・税務業務を行う ・現金預金の管理・伝票作成・帳簿記録・経費精算・給与計算・年末調整・決算書作成など 福利厚生 Big4などの大手税理士法人以外では手薄な事務所が多い 企業によるが一般的な会計事務所よりは手厚い傾向 キャリアパス ・経理・会計事務所・コンサルティングファーム・監査アシスタント・独立開業(税理士のみ) ・経理・経営企画・内部監査・金融業界・監査アシスタント 会計事務所と経理における「業務内容」の違い まず、業務内容における最も大きな違いは、会計事務所がクライアント企業の経理・税務業務を代行するクライアントワークであるのに対し、事業会社の経理は自社の経理・税務業務を担う点です。 会計事務所では多様な業界の会計知識を習得できますが、経理では自社の事業に特化した実務知識が深まります。 また、コミュニケーションの相手も異なり、会計事務所では主にクライアント、経理では社内の従業員や経営陣とのやりとりが中心になります。 さらに、福利厚生を比較すると、一般的に会計事務所よりも事業会社の経理の方が整っている傾向があります。 ただし、Big4のような大手税理士法人では、企業に近いレベルの福利厚生がある場合もあり、最近では労働環境の改善に積極的に取り組み、事業会社以上に働きやすい環境の会計事務所もあります。 MS-Japanが主催する優良会計事務所を表彰するアワード「 Best Professional Firm」を受賞している会計事務所を参考にするとよいでしょう。 会計事務所と経理における「キャリアパス」の違い 事業会社の経理は、経理職としてのキャリアを深めるだけでなく、経営企画や内部監査などの管理部門にもキャリアを広げやすいのが特徴です。 一方、会計事務所では、働きながら税務を学び、税理士資格を取得できれば、独占業務である税務の代理・税務書類の作成・税務相談に携わることができます。 また、税理士資格を活かして独立開業することも可能です。 あわせて読みたい 経理とは?仕事内容一覧とやりがい、年収など詳しく解説! 会計事務所の仕事内容・スキル・働き方 会計分野の転職アドバイスを受ける 会計事務所から経理に転職するための準備 会計事務所から事業会社の経理に、納得のいく転職を実現するためには、戦略的な準備が不可欠です。ここでは、転職成功率を高めるための4つのポイントを解説します。 転職の目的を明確にする 最も重要な準備は転職の目的を明確にすることです。 「なぜ会計事務所ではなく、企業の経理に転職したいのか」「事業会社の経理に転職して何を成し遂げたいのか」など、転職を通して実現したいことを、具体的に言語化することが大切です。 志望動機の作成や面接対策にも役立つほか、応募先企業を迷いなく選べるようになります。 複数社から内定を獲得できた際も、転職の目的に立ち返ることで、入社先を選びやすくなるでしょう。 譲れる条件・譲れない条件を決める 転職の目的を叶えるために、譲れる条件と譲れない条件を決めましょう。 すべての希望条件を満たす転職先は、希少で競争率も高い傾向があります。そのため、転職先に求める条件の中で優先順位を決めることが重要です。 転職の目的がスキルアップであれば、必ず従事したい業務や裁量権の範囲、ワークライフバランスの改善であれば、許容できる残業時間などを具体的に決めましょう。 応募先の業界を絞り込む さまざまな企業の会計・税務に携われる会計事務所と異なり、事業会社の経理は所属する企業の経理業務のみを担当します。 事業会社の経理では、所属する業界に特化した会計知識やスキルが求められます。 会計事務所でさまざまな業界のクライアントと関わる中で、興味のある業界を見つけておきましょう。 士業と経理に詳しい転職エージェントを利用する 会計事務所から経理へ転職する際は、転職エージェントを活用するとよいでしょう。 特に事業会社での経験がない場合は、業界・職種の違いをよく理解する必要があります。 士業と経理のどちらも詳しい転職エージェントであれば、転職活動に役立つ情報を提供してもらうことができるでしょう。 また、転職エージェントでは、希望条件に合った求人の紹介だけでなく、キャリアアドバイザーのカウンセリングによるキャリアの棚卸しやアピールポイントの洗い出し、応募書類の添削、面接対策など、さまざまな転職サポートをすべて無料で提供しています。 \求人紹介から選考対策も!/ 無料の転職サポートを受ける 会計事務所から経理へ転職する際の志望動機の考え方 会計事務所から経理への転職における志望動機は、「経理」を志望した動機と「応募先企業」を志望した動機に分けて考えることが重要です。 具体的には、「なぜ会計事務所ではなく経理を目指すのか」「なぜ他企業ではなく応募先企業で働きたいのか」を言語化しましょう。 そこで重要になるのが、自己分析と業界研究・企業研究です。 「クライアントワークではなく、自社の一員として経理業務を通じて組織に貢献したい」「応募先企業の事業内容に魅力を感じ、自身の会計事務所での経験を活かして積極的に経理業務に携わりたい」など、具体的に伝えることで評価につながります。 無料で経理専門の転職支援を受ける 【資格別】会計事務所経験者の自己PRとは 会計事務所経験者が事業会社の経理を目指す場合、どのような経験・スキルがアピールポイントになるのでしょうか。 ここでは、税理士資格保有者と、税理士試験科目合格者、無資格(事務員など)に分けて、アピールポイントを解説します。 税理士資格保有者 税理士資格は、事業会社の経理職においても一定の評価を得られる強みです。 とはいえ、企業の採用では資格以上に、実務経験や人柄が重視されることも多く、これまで培ってきた知識や実績をどのように企業で活かせるかを具体的に伝えることが求められます。 たとえば、大手上場企業では税務部門が独立しているケースが多いため、税務申告やタックスプランニングなどの経験が選考で評価されやすいでしょう。 一方で中小規模の企業では、税務だけでなく、決算、管理会計、給与計算、会計ソフトの導入支援といった幅広い業務経験が役立ちます。 また、IPO準備中のベンチャー企業などでは、経理体制の立ち上げや業務フローの構築に関与した経験がある場合、大きな強みとなります。 応募先の企業がどのようなフェーズにあるかを見極めたうえで、マッチする経験・スキルを重点的に伝えると効果的です。 さらに、事業会社ではチームでの協働や他部署との連携も重要となるため、顧問先や所内スタッフとの関係構築に関する具体的なエピソードを盛り込むと、人物面でのアピールにもつながります。 税理士科目合格者 税理士資格を保有していなくても、税理士科目に合格していればアピールポイントになります。 応募書類には、合格した科目と合格した時期を明記しましょう。 合格科目が会計事務所の実務でどのように活かされていたか、そして応募先企業ではどのように役立てられるかを説明できるようにしましょう。 事業会社の経理で特に評価されるのは、「簿記論」と「財務諸表論」です。 経理業務のベースとなるため、実務でも十分に活かせるでしょう。 企業規模が大きくなるほど会計処理が複雑になるため、高度な簿記の知識を持っていることはアピールポイントになります。また、企業規模を問わず法人税の申告業務が発生するため、「法人税」も高い評価を得ることができるでしょう。 税理士の科目合格者の場合、「税理士を諦めたから転職している」と受け取られ、マイナスの印象を与える可能性があります。 このイメージを払拭するためには、「クライアントとして外部から支援するのではなく、事業の当事者として企業の成長に貢献したい」など、経理職を志望する前向きな理由を伝えることが重要です。 これによって、キャリアチェンジへの意欲を効果的にアピールできます。 無資格(事務員など) 税理士資格や科目合格などのアピールポイントがない場合も、会計事務所で働いていた実績は評価されます。 ただし、経理への転職を想定した場合、評価の対象になるのは会計関連の実務経験です。 どの程度まで積んできたのかを明確にし、経理として活躍の余地があることをアピールすることが重要です。 当然、税理士資格保有者や科目合格者と比較すると、不利になりますが、経理スタッフのポジションであれば可能性はあります。少しでも評価を高めるために、日商簿記2級を取得しておくことをおすすめします。 また、スキルや専門知識以外にも、チームで成し遂げた実績やコミュニケーション能力など、実務とは別の切り口のアピールポイントも準備しましょう。 応募先企業の社風や組織文化と、自身の人柄が合っている点もアピール材料になります。 「真面目にコツコツと」「几帳面な性格で」などの抽象的な表現は印象に残らないため、具体的な数値やエピソードを交えて伝えるとよいでしょう。 無料で転職アドバイスを受ける 「会計事務所経験者歓迎」の経理求人例 ここでは、管理部門・士業特化型転職エージェント「MS-Japan」で取り扱っている会計事務所経験者歓迎の経理求人の一部をご紹介します。 ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。 【経理財務マネージャー候補】プライム上場グループ/成長中Fintech/リモートワーク可 仕事内容 ・当社および関連グループ会社の月次・年次決算業務の推進 ・加盟店向け精算業務の運用・改善 ・事業部門との連携による収益・原価管理の高度化 ・新規事業、サービスに関する会計・税務論点の整理・制度設計 必要な経験・能力 ・事業会社または会計事務所での経理実務経験5年以上(特に非定型・イレギュラー処理のご経験がある方) ・業務フロー設計・改善のプロジェクト経験 想定年収 700万円 ~ 1,000万円 大手メーカーからカーブアウトした企業/経理・債権債務管理担当 仕事内容 ・決算業務・債権債務管理 ・内部統制・SOX対応 ・予算策定および実績分析 ・外部監査対応 必要な経験・能力 ・事業会社または会計事務所で、決算業務における債権債務管理の実務経験(業界不問) ・損益計算書・貸借対照表作成分析業務 ・予算/見通し策定分析業務 ・会計士監査対応 想定年収 480万円 ~ 870万円 大手セキュリティ会社の経理スタッフを募集/リモートワーク 仕事内容 ・日常経理業務(日次/月次) ・単体決算業務(月次/四半期/年次) ・税務対応 ・予算編成、予実管理 ・管理会計(財務分析) ・会計監査対応 必要な経験・能力 ・事業会社もしくは会計事務所での経理実務経験(目安2.3年以上) ・PCスキル(Excel、Word) ・日商簿記検定2級程度の資格、または同等の知識をお持ちの方 想定年収 500万円 ~ 700万円 業界最大級の求人数から探せます 経理・財務の求人はコチラ 会計事務所から経理に転職した事例 「MS-Japan」を利用して、会計事務所から事業会社の経理へ転職した方の事例をご紹介します。 スキル向上と自己分析の準備で、会計事務所から大手企業経理に転職した事例 Aさん(20代男性)簿記2級 転職前:会計事務所 転職後:大手上場企業 経理 会計事務所に4年ほど勤めていたAさんは、税務会計業務を一通り経験し、新しい挑戦をしたいと考えました。 このまま会計事務所業界でキャリアを積むか、事業会社の経理に進むか迷っていました。 しかし、クライアント対応を通じて企業内部の会計に興味を持ち、データ分析や業績評価への関心が高まったことから、経理職への転職を決意しました。転職決意後、スキル向上のためにオンラインの専門コースを受講し、Excelによるデータ分析や財務報告スキルを高める学習に取り組みました。 その後「MS-Japan」経由で大手企業の経理部門へ応募し、面接では過去の実績や新たに身につけたスキルを具体的に示し、成長・貢献の意欲をアピールしたことで内定を獲得しました。Aさんの転職成功のポイントは、徹底した自己分析です。 会計事務所と経理の業務は類似点が多いものの、関わり方や進め方などが異なります。 そのためAさんは、経験業務と知識を洗い出し、そのスキルがどの経理業務で活かせるか、また足りない部分の補完方法などについて考えました。 ご自身に足りなかったExcelスキルを身につけ、今までの実績とともに成長意欲を的確にアピールしたことで、転職成功へとつながりました。▶ Aさんの事例を詳しく読む子育てとの両立を条件に、成長企業への転職を叶えられた40代女性の事例 Kさん(40代前半女性)税理士、TOEIC860 転職前:個人会計事務所(10名規模) 転職後:非上場企業 経理(180名規模) 複数の会計事務所で個人・地元の中小企業を中心とした一連の会計・税務業務に従事していたKさんは、さまざまなクライアントを担当する中で事業会社の経理に興味を持ち始めました。 しかし、保育園に通うお子さんがいたため、送迎の時間や残業対応などの制約があり、転職した場合に仕事と家庭の両立ができるのか不安もありました。「MS-Japan」では、過去にKさんと同じ境遇の方を紹介し内定に至った企業や、柔軟な働き方を推進している企業など、さまざまな提案をさせていただきました。 事前に「MS-Japan」から応募先企業へのフォローを入れる機会もありましたが、面接でKさんの人柄を知っていただき、Kさんからご自身の事情と希望を伝えたことで、働き方についてのすり合わせができました。最終的に、Kさんの前向きで主体的な働きぶりが評価され、新規事業を展開する成長企業から内定を獲得し、家庭と仕事を両立できる環境で、新たな一歩を踏み出されました。 ライフイベントに変化があると、仕事と家庭との両立が難しくなることもありますが、「MS-Japan」とともにすり合わせを重ねることで、顕在化している企業側のニーズを探ることができます。 子育てに理解のある企業の紹介や、希望に沿う働き方・自身のキャリアを諦めずにステップアップしていくことも可能です。▶ Kさんの事例を詳しく読む いつかは転職したい方向け!経理・財務職のための個別相談会 詳しくはこちら まとめ近年、会計事務所での経験は、事業会社の経理職においても高く評価される強力な武器となります。 クライアントワークで培った多様な業界知識や税務の専門性は、即戦力として大きなアドバンテージになるでしょう。転職を成功させる鍵は、①なぜ事業会社の経理なのか(Why)、②そこで何を成し遂げたいのか(What)を明確にし、③自身の経験を応募先企業のニーズに合わせて具体的にアピールすること(How)です。この記事で解説したポイントを押さえ、戦略的に準備を進めることで、理想のキャリアチェンジを実現できるはずです。 転職活動における自己分析や企業研究、キャリアプランの構築などでお悩みの場合は、士業・管理部門特化型転職エージェント「MS-Japan」にご相談ください。