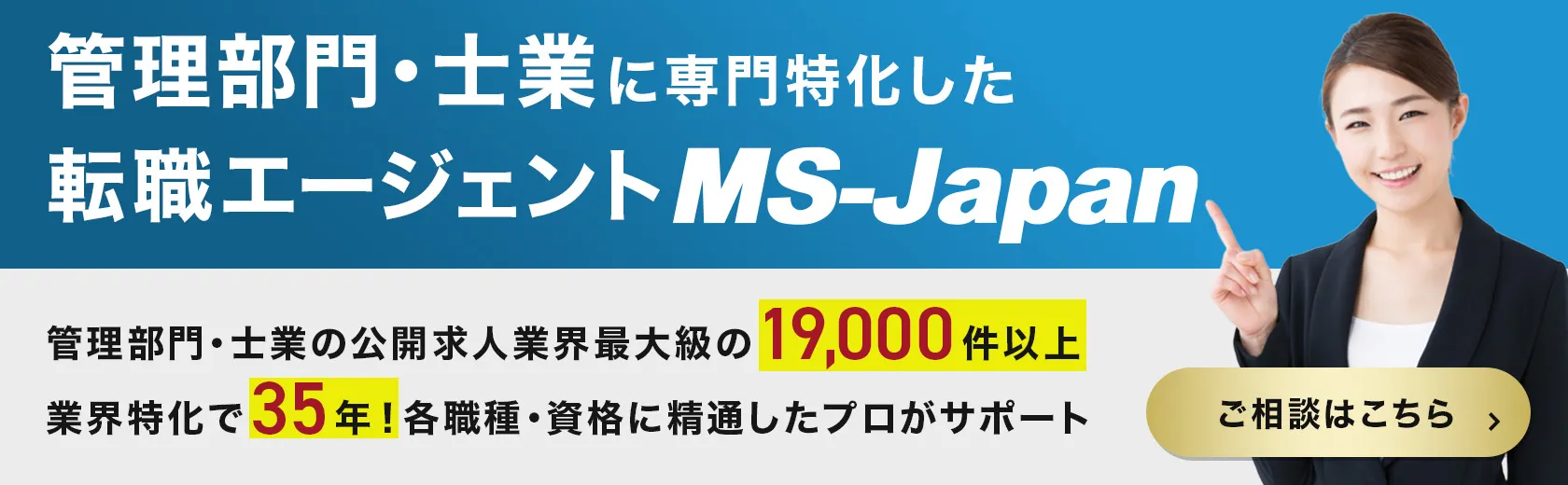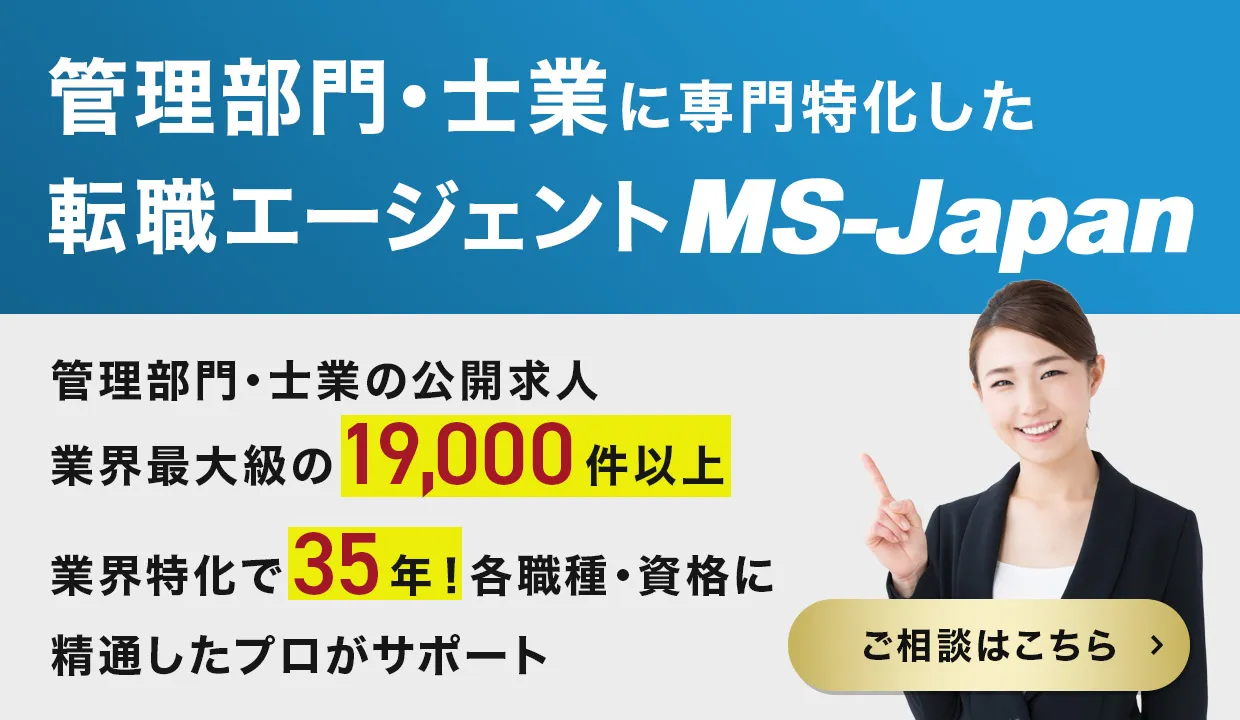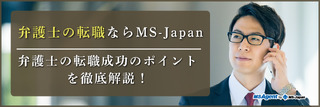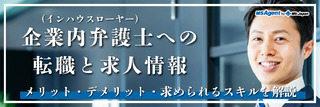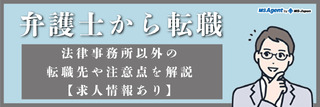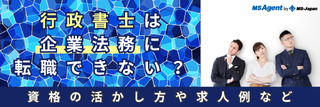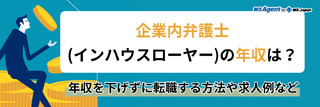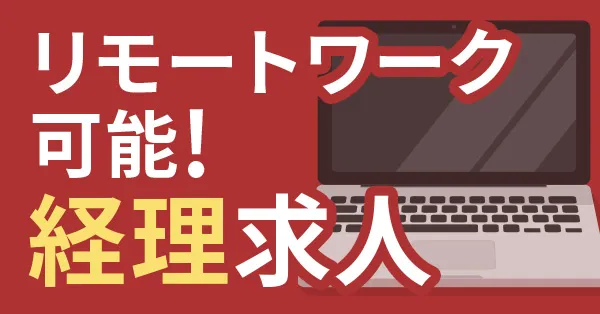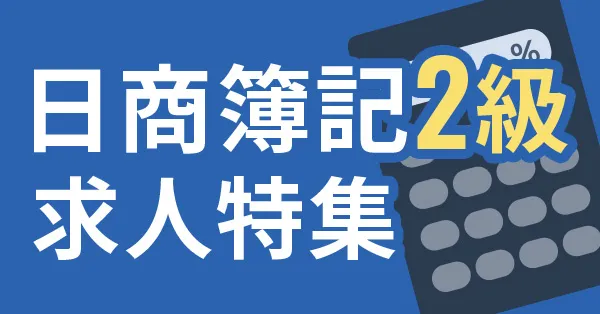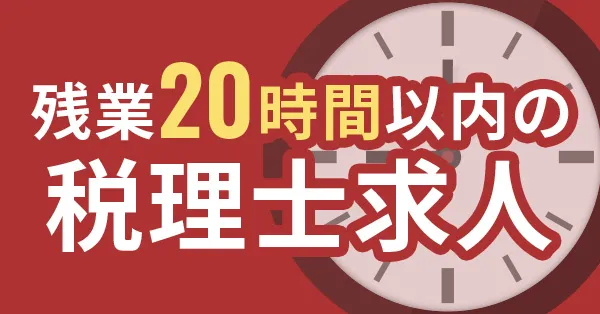弁護士のダブルライセンス~中小企業診断士編~

弁護士人口が増えるにつれて、同業者同士の顧客獲得競争も激しくなっています。そこで、差別化を図るために、別の資格を取得する弁護士が増えています。その有力候補として注目されている資格の一つが「中小企業診断士」です。弁護士が中小企業診断士の資格を取得すると、どのような新しい強みを得ることができるでしょうか。
中小企業診断士とは?
中小企業診断士は国家資格の一つであり、中小企業の経営状態を診断して、課題を明らかにし、その解決のために適切なアドバイスを送る専門職です。中小企業支援法という法律において、中小企業診断士の業務は「経営の診断及び経営に関する助言」(11条)と定義されています。日本国内にある企業のうち、99%以上が中小企業に分類され、その活動の総体が日本経済を支えているといえます。ただし、多くの中小企業が赤字経営に苦しんでいるのが実態です。
そこで、中小企業診断士が実質的には中小企業向けの経営コンサルタントのような役割を果たし、それぞれの企業が持つ経営資源を最大限に活かして、将来の成長戦略に基づいた目標を策定し、その戦略を実行に移すために必要な助言やサポートを行います。
弁護士が、中小企業診断士の資格も取得する意義とは?
弁護士法3条2項では「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる」と定めています。つまり、弁護士資格を取得すれば、弁理士試験や税理士試験に合格しなくても、弁理士や税理士の職務を行うことができるという、一種の特権があるのです。一方で、中小企業診断士に関しては、弁護士資格を持っていれば関連業務を遂行できるという定めはありません。
しかし、中小企業診断士に独占業務は無いものの、弁護士資格を取得するにあたって吸収した知識のみでは、中小企業診断士が携わる業務もカバーできるとは言い難いのです。
中小企業診断士試験の科目は、司法試験の科目とほとんど重なっていません。税理士試験や弁理士試験だって、司法試験との共通科目や重複部分が決して多いわけではありません。ただ、法曹に求められる知識やスキルと、中小企業診断士に求められる知識やスキルとでは、大きく異なっていると考えられているのでしょう。
以下に、中小企業診断士の試験概要をご紹介します。
<1次試験>
中小企業診断士試験は、1次試験がマークシート式の選択問題で、「経済学・経済政策」「財務・会計」「企業経営理論」「運営管理(オペレーション・マネジメント)」「経営法務」「経営情報システム」「中小企業経営・中小企業政策」の7科目が問われます。
この中で、司法試験と重なる科目があるとすれば、「経営法務」です。この中で、民法・会社法・知的財産法・倒産法といった、民事系の諸法制が幅広く問われることになります。もちろん、弁護士であれば満点近く得点できるような基本的な内容ですが、「経営法務」は、あくまで7科目中の1科目にすぎませんので、試験全体に占める比重は決して重くありません。
中小企業診断士に求められるのは、経営学もさることながら、経済学や会計学まで、実践的な社会科学の幅広い知識といえます。もし、弁護士が中小企業診断士の資格まで取得できれば、法律というフィールドを離れても、世の中の経営者と対等以上の関係で対話できるようになるはずです。
中小企業診断士の1次試験は、7科目それぞれで「科目合格制」が採用されているのが特徴です。7科目すべてで一度に合格点(正答率60%以上)を取らなくても、合格点をクリアした科目は個別に、その後3年間にわたって合格の事実を引き継ぐことができます。よって、学習時間の限られている社会人でも、計画的に取り組みやすいのです。
<2次試験>
2次試験は、筆記(論述)方式と、口述(面接)方式で、分けて行われます。「中小企業の診断及び助言に関する実務の事例」という実践的な内容に沿って、「人事・組織」「マーケティング・流通」「生産・技術」「財務・会計」を対象に、幅広く正確な知識が問われます。
2次試験について、科目別合格はありませんが、1次試験の合格資格が2年間有効となっています。仮に2次試験に不合格となってしまっても、翌年は1次試験をパスして、2次試験から受けられます。
やはり、受験勉強に割く時間をあまり取れない社会人受験者にとっては、取り組みやすいルールになっています。弁護士も、働きながら中小企業診断士の資格を取るとすれば、このような特典を有効活用しながら、次の受験に必要な科目を集中的に攻略すると、効率的な受験対策ができるでしょう。
弁護士が中小企業診断士を取得すると、強みが増える

以上のように、司法試験と中小企業診断士試験の間には、重複がほとんどありません。つまり、中小企業診断士の資格を持つ弁護士は、他の弁護士と比べても、ビジネスの現場における問題解決に即した実践的知識を身につけていることになります。
また、企業経営者が弁護士に顧問をお願いするにしても、経営コンサルタントの国家資格に相当する中小企業診断士の資格がある弁護士に相談すれば、話が早いのです。
中小企業診断士 兼 弁護士は、法律論だけでなく、経営者の視点で会話をすることができるので、様々な角度から多様な問題解決策を提示することができます。また、経営者の立場としては、顧問弁護士と中小企業診断士に別々に相談するよりも、手間や費用を節約できるメリットがあります。
まとめ
弁護士は、司法書士や行政書士などと顧客が競合する関係にありますが、弁護士と中小企業診断士それぞれの役割は上手く棲み分けができています。裏を返せば、弁護士が中小企業診断士の資格を取得すると、今まで関わりのなかったタイプのクライアントと新たな関係を結べる可能性が高まります。時間やエネルギーに余裕のある弁護士は、ぜひチャレンジしてみてください。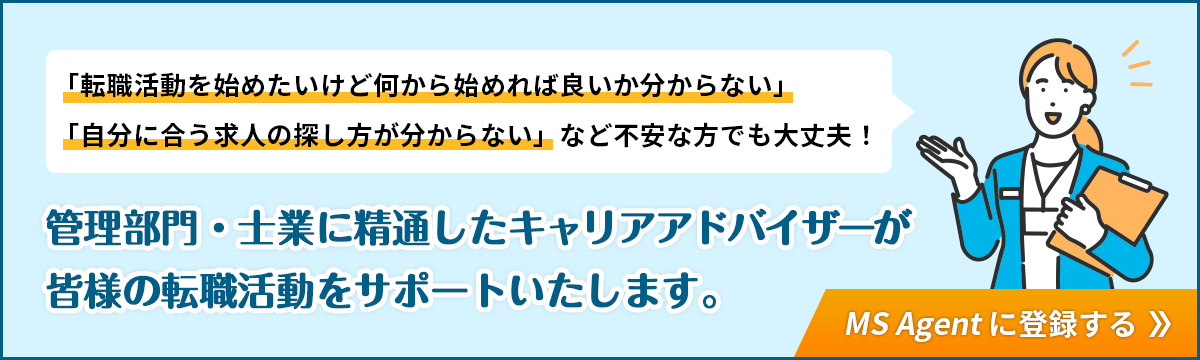
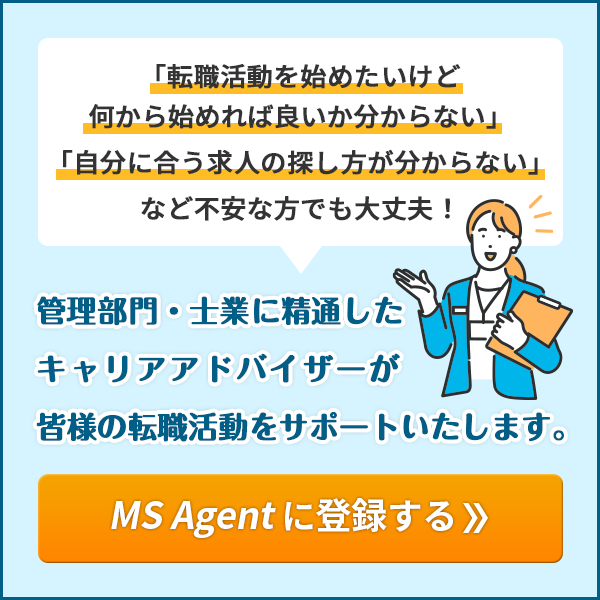
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事

【2025年司法試験に強い大学ランキング】司法試験の合格率が高い法科大学院は?

会社法改正は法務人材のキャリアをどう変える?転職市場で評価される知識と経験(後編)
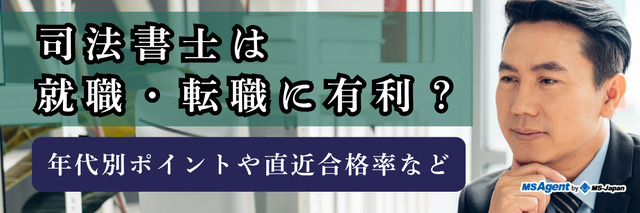
司法書士は就職・転職に有利?年代別ポイントや直近合格率など
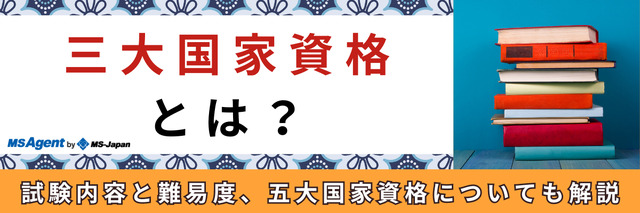
三大国家資格とは?試験内容と難易度、五大国家資格についても解説
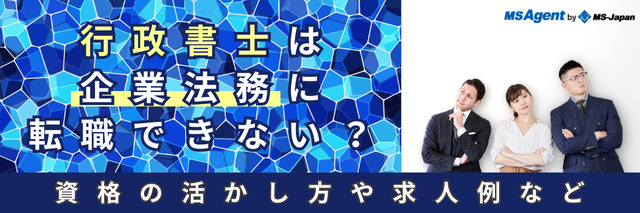
行政書士は企業法務に転職できない?資格の活かし方や求人例など
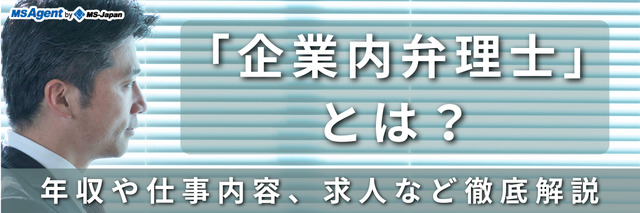
「企業内弁理士」とは?年収や仕事内容、求人など徹底解説
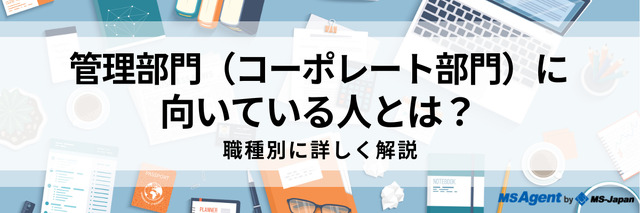
管理部門(コーポレート部門)に向いている人とは?職種別に詳しく解説

未経験でも転職はできる?MS-Japanの転職支援サービスを紹介!
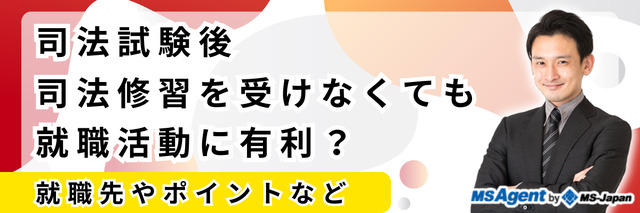
司法試験後、司法修習を受けなくても就職活動に有利?就職先やポイントなど