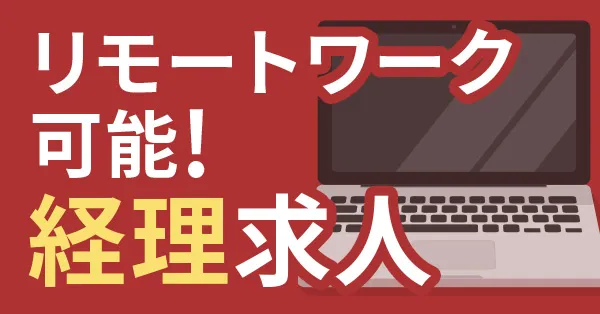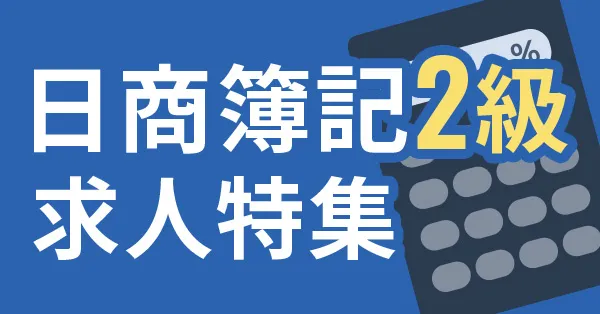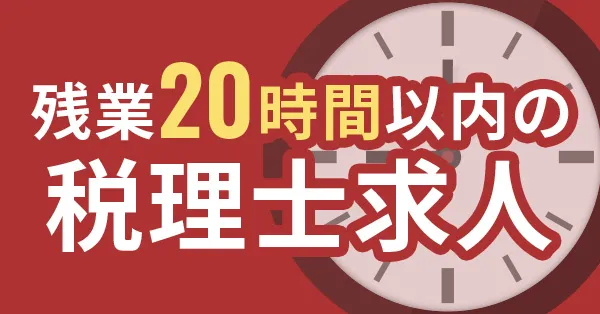司法試験と司法書士試験の違いは?司法試験の学習経験は司法書士にも活かせる!
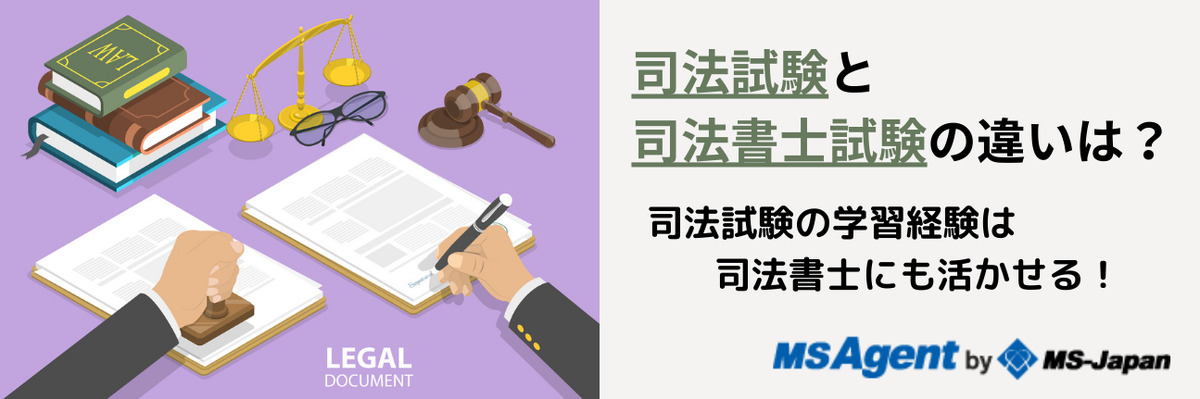
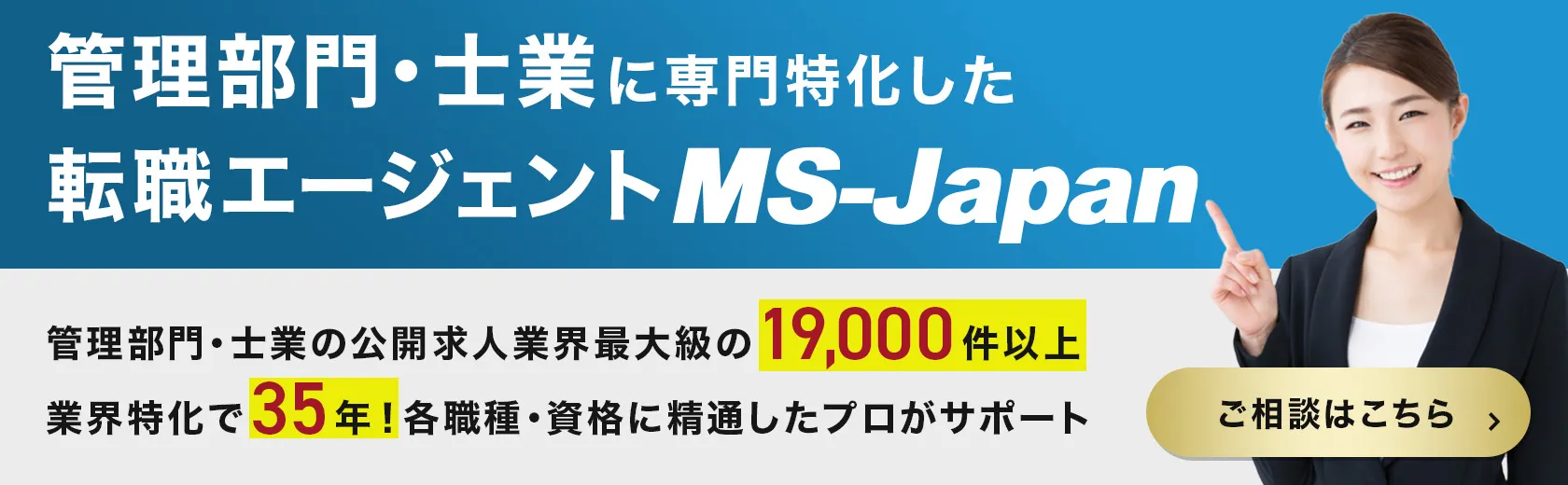
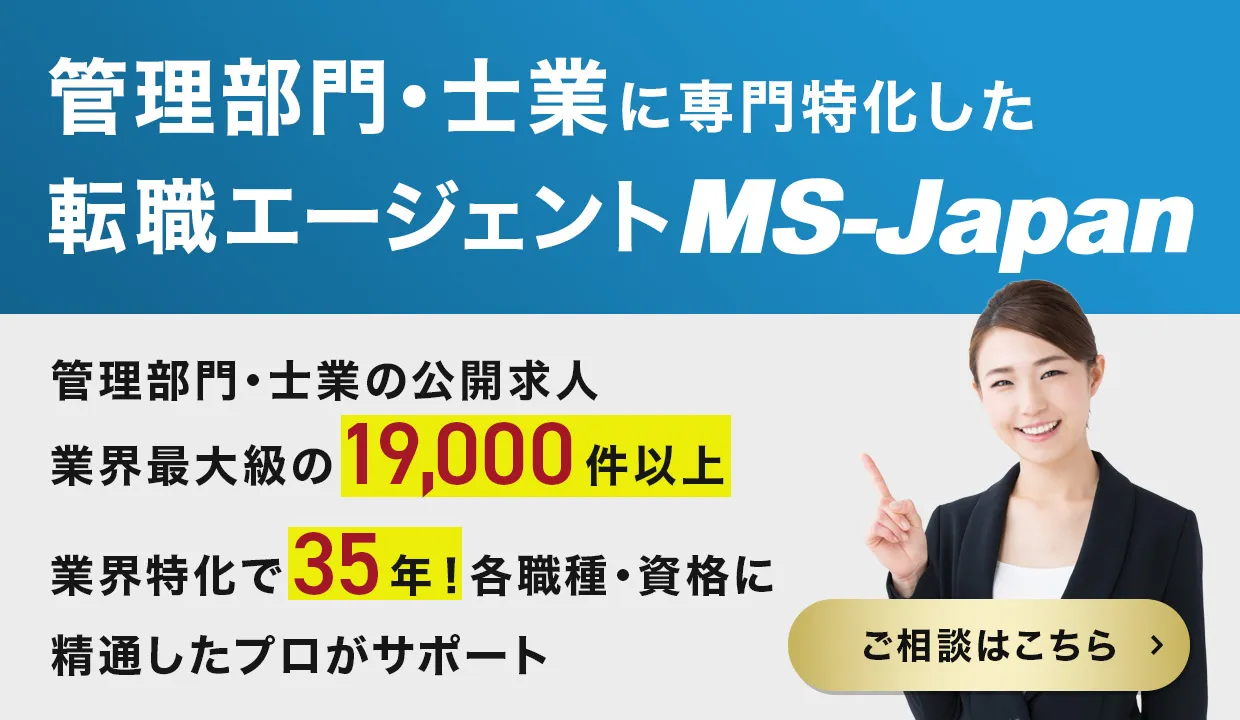
司法試験の受験経験がある方の中には、「司法書士の資格をとろうか」と考えている方もいることと思います。
司法書士は、弁護士とならぶ「8士業」の1つとなり、独占業務を与えられています。
司法書士試験は、司法試験と試験科目が重なるものも多いため、司法試験の学習経験を活かすことも可能です。
この記事では、司法試験と司法書士試験は一体何が違うのか、そして司法試験の学習経験を活かして司法書士を目指すためのポイントについて見ていきましょう。
・司法試験と司法書士試験は共通科目があり、司法試験を受験した経験は、司法書士試験を受験するうえで大きなアドバンテージとなる
・就職経験がない場合でも、司法試験を受験した経験を評価してくれる企業があるため、就職のために司法書士を受験するのは慎重に考える必要がある
司法試験と司法書士試験の違い
それでは最初に、司法試験と司法書士試験の違いについて、試験科目と難易度のそれぞれの面から見てみましょう。
1.試験科目
司法試験と司法書士試験の試験科目は、それぞれ以下の通りです。
司法試験
司法試験は毎年7月に行われます。試験の日程は、論文式試験が3日間、短答式試験が1日の計4日間です。
論文式試験の科目は、公法系科目(憲法および行政法)、民事系科目(民法、商法および民事訴訟法)、刑事系科目(刑法および刑事訴訟法)、および選択科目(知的財産法、労働法、租税法、倒産法、経済法、国際関係法、環境法から1科目を選択)の4科目。
短答式試験の科目は、憲法、民法、および刑法の3科目です。
司法書士試験
司法書士試験は、7月に筆記試験が行われ、それに合格した人に対して10月に口述試験が行われます。
7月の試験は、午前の部と午後の部に分かれています。
午前の部で行われる試験の科目は、憲法、民法、商法(会社法、およびその他の商法)および刑法で、これらはいずれも択一式で35問出題されます。
午後の部で行われる試験の科目は、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、司法書士法、供託法、不動産登記法、および商業登記法で、択一式35問、書式2問(不動産登記法1問、商業登記法1問)が出題されます。
以上のように、司法試験と司法書士試験の試験科目は、異なりはするものの、憲法、民法、刑法、商法および民事訴訟法が共通科目となっていることがわかります。
参考:
令和7年度司法試験受検案内|法務省
令和7年度司法書士試験受検案内書|法務省
2.難易度
司法試験と司法書士試験では、難易度はどの程度違うのでしょうか。
司法試験の2024年の合格率は42.1%。それに対して司法書士試験の2025年の合格率は5.2%でした。
これだけ見ると、「司法書士試験の方がむずかしい」と思うかもしれません。
しかし、司法書士試験は誰でもが受験できるのに対し、司法試験は、法科大学院を修了する、あるいは予備試験に合格することが受験資格となっています。
したがって、司法書士試験は法律を全く勉強したことがない人でも受験している可能性があるのに対し、司法試験は、法律をみっちり勉強した人だけが受験します。
そう考えれば、合格率だけを見て難易度を比較することはできません。
参考:
令和6年度司法試験の結果について|法務省
令和7年度司法書士試験の最終結果について|法務省
司法書士は役に立つ資格なのか?
司法書士は、役に立つ資格です。
司法書士はまず、
・登記または供託に関する手続きについて代理する
・法務局や裁判所、検察庁に提出する書類を作成する
の独占業務を持っています。
また、2002年に誕生した認定司法書士制度により、司法書士の業務の範囲が大幅に広がりました。
特別研修を受け、考査試験に合格すると、簡易裁判所での140万円以内の民事訴訟について、弁護士と同様に代理ができるようになっています。
弁護士は、法律業務を基本的には無制限に行うことができます。
それに対して司法書士は、弁護士と比較すれば業務に制限があるとはいえます。
しかし、弁護士は都市部に集中しています。
特に弁護士が少ない地域などでは、法律について身近に相談できる存在として、司法書士は十分に活躍できるといえるでしょう。
司法試験の学習経験を活かして司法書士を目指す
司法試験を受験した経験は、司法書士試験を受験するうえで大きなアドバンテージとなります。
なぜならば、司法試験と司法書士試験とで共通する受験科目があるからです。
上で見た通り、司法試験と司法書士試験とでは、憲法、民法、商法および民事訴訟法が共通科目となっています。
もちろん、司法試験と司法書士試験とでは、同じ科目でも重視されるポイントは異なります。
しかし、司法試験に向けて勉強した経験は、司法書士試験を受験するために大きく役に立つことは間違いがありません。
司法書士をとらなくても働き口はあるか?
「司法書士の資格をとろうか」と考える理由として、「就職先を見つけるため」である方もいることでしょう。
たしかに、司法書士の資格があれば、就職先の選択肢は大幅に広がります。
しかし、司法書士の資格がなくても、就職先を見つけることは可能です。
就職経験がない場合でも、司法試験を受験した経験を評価してくれる企業があるからです。
もし司法書士の資格をとるのが就職のためだけならば、すぐに就職活動を始めたほうが、早く就職できることになるでしょう。
まとめ
司法試験の受験経験を活かすことが可能となる司法書士試験の受験。
しかし、就職のためだけならば、なにも司法書士試験の準備のために時間をかける必要はありません。
自分が何のために司法書士試験を受けるのか、慎重に考える必要があるでしょう。
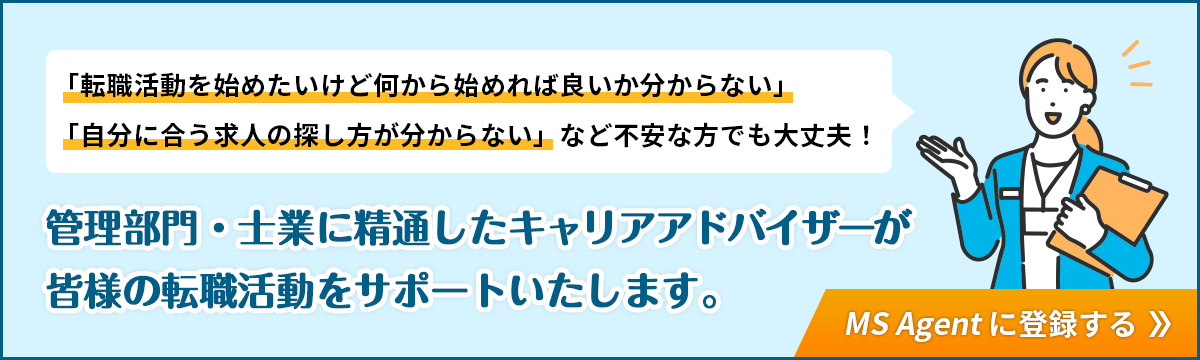
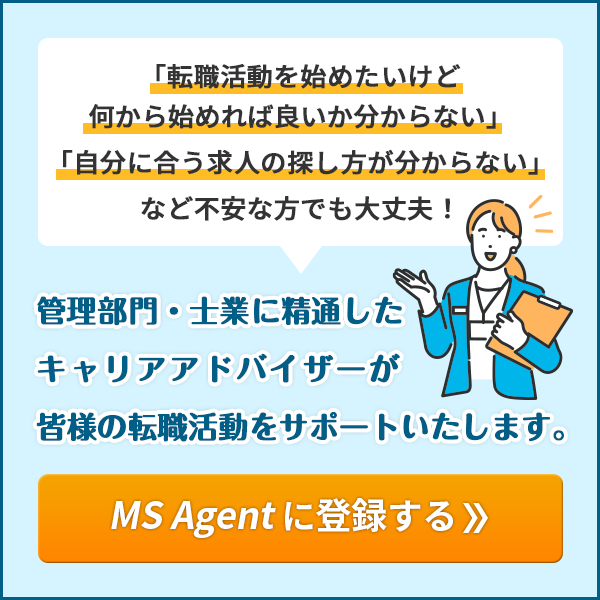
この記事を監修したキャリアアドバイザー

大学卒業後、新卒でMS-Japanに入社。
法律事務所・会計事務所・監査法人・FAS系コンサルティングファーム等の士業領域において事務所側担当として採用支援に従事。その後、事務所側担当兼キャリアアドバイザーとして一気通貫で担当。
会計事務所・監査法人 ・ 法律・特許事務所 ・ コンサルティング ・ 金融 ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ 税理士科目合格 ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事

予備試験とは?試験概要や科目、日程など
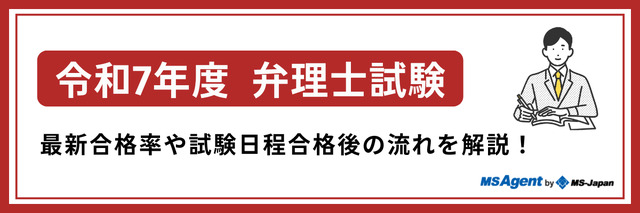
令和7年度弁理士試験|最新合格率や試験日程、合格後の流れを解説!
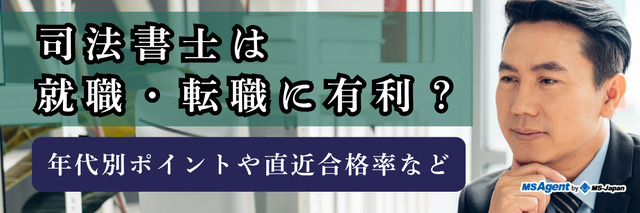
司法書士は就職・転職に有利?年代別ポイントや直近合格率など
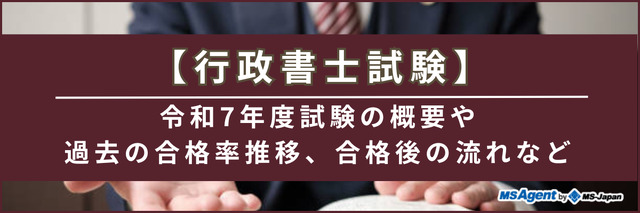
【行政書士試験】令和7年度試験の概要や過去の合格率推移、合格後の流れなど
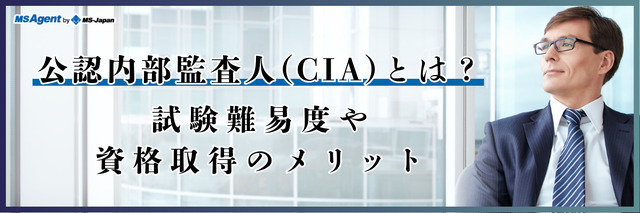
公認内部監査人(CIA)とは?試験難易度や資格取得のメリット
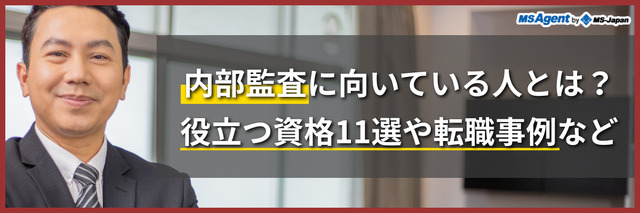
内部監査に向いている人とは?仕事内容や役割、資格について解説
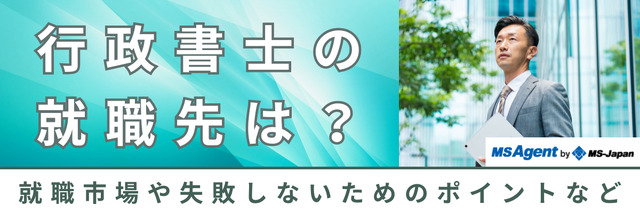
行政書士の就職先は?転職市場や失敗しないためのポイントなど
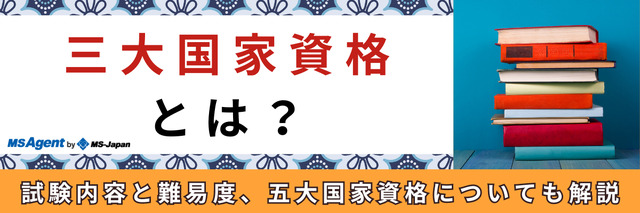
三大国家資格とは?試験内容と難易度、五大国家資格についても解説
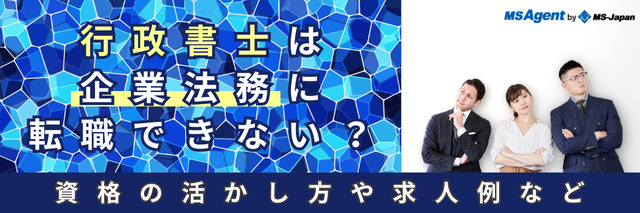
行政書士は企業法務に転職できない?資格の活かし方や求人例など
サイトメニュー


業界最大級の求人数・転職支援実績!管理部門・士業の転職に精通した専門アドバイザーがキャリア相談~入社までサポートいたします。
新着記事
求人を職種から探す
求人を地域から探す
セミナー・個別相談会


業界最大級の求人数・転職支援実績!管理部門・士業の転職に精通した専門アドバイザーがキャリア相談~入社までサポートいたします。