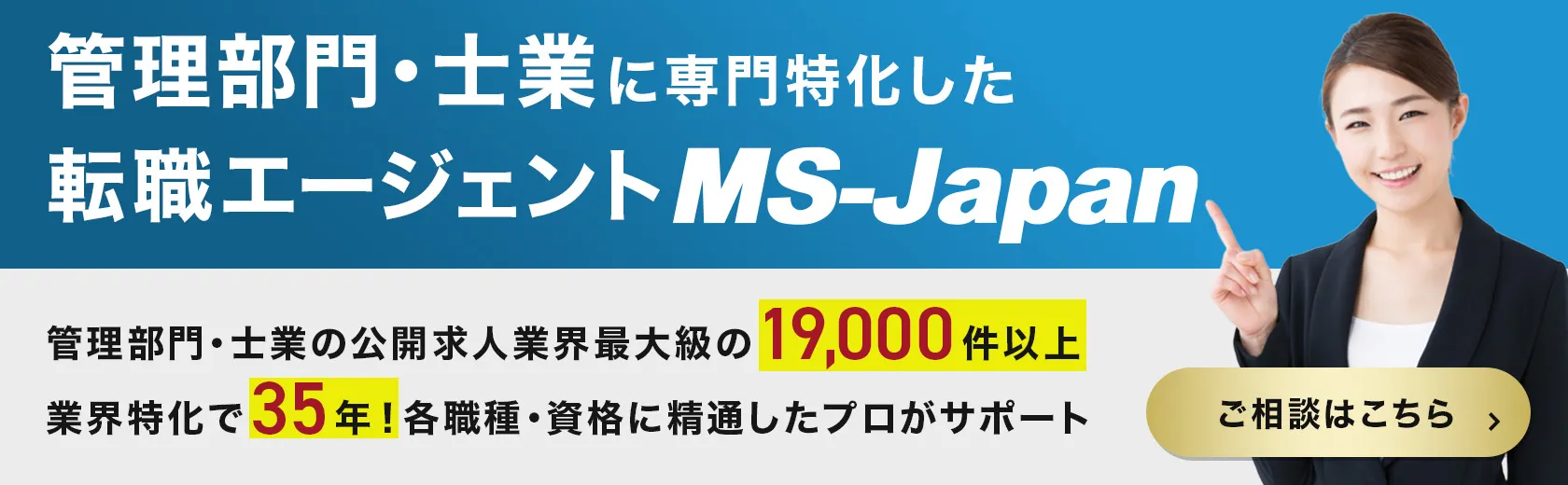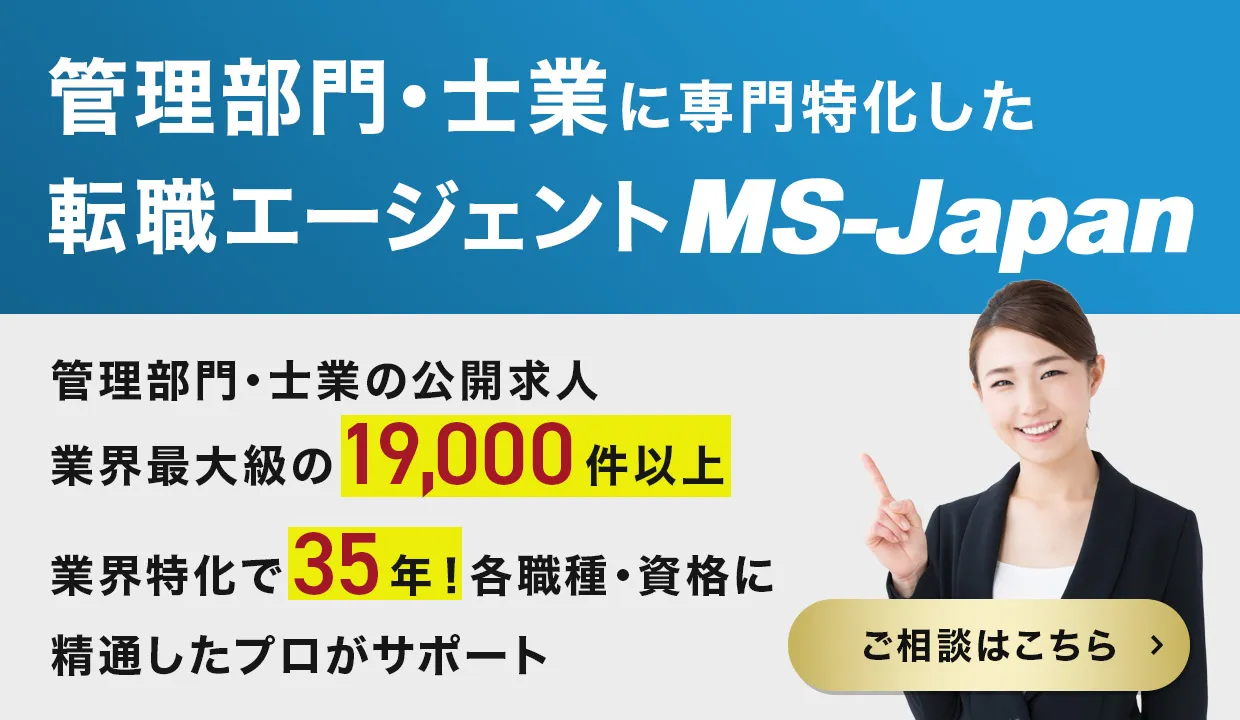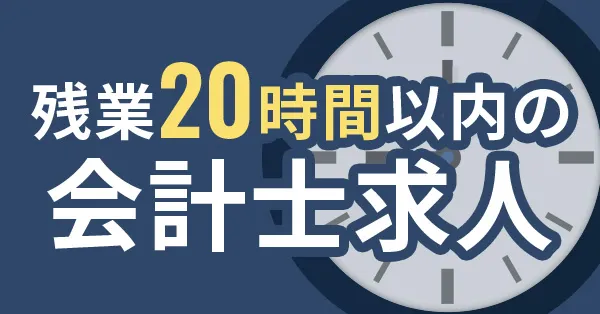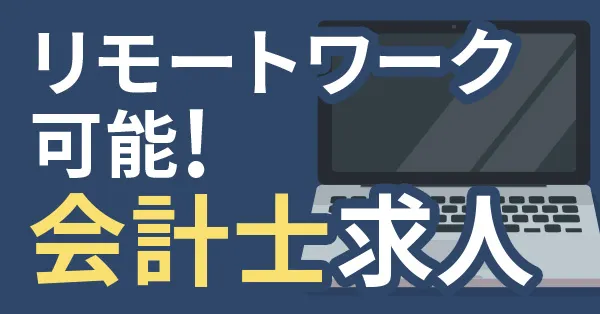公認会計士の独立|注意点やメリット・デメリット、必要な準備など
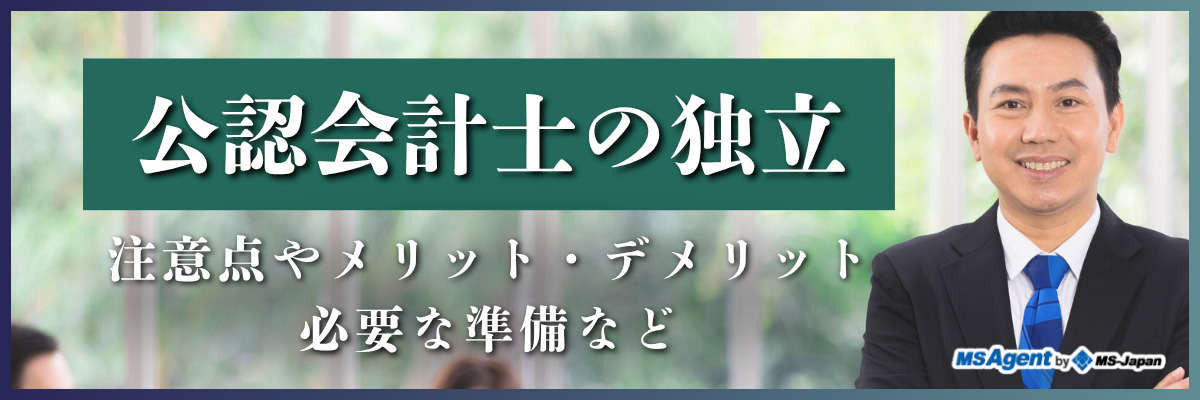
監査法人に勤める公認会計士の中には、将来的な独立を見据えて準備を進めている方も少なくありません。
本記事では、独立を目指す公認会計士に向けて、独立のメリット・デメリットや、準備すべきポイントを解説します。
公認会計士が独立するメリットとは?
ここでは、公認会計士が独立する3つのメリットを解説します。
高年収を実現できる可能性がある
1つ目のメリットは、高年収を実現できる可能性があることです。
公認会計士として独立した場合、自身の実力や努力により、通常のサラリーマンと比べて高い収入を得る可能性があります。
自身のパフォーマンスが直接収入に影響するため、スキルと経験を最大限に活用することが重要です。
会社員の場合は、どれだけ昇進しても年収に上限があるのに対し、公認会計士が独立すると年収に上限がなくなるため、場合によっては年収2,000万円以上を目指すこともできます。
さまざまな業務に挑戦することができる
2つ目のメリットは、さまざまな業務に挑戦できることです。
独立した公認会計士は自ら仕事を選べるため、さまざまな業界や企業、ビジネスモデルに関わる機会が広がります。
これによって広範で深い知識を獲得し、自身のスキルセットを拡大することが可能です。
ただし、採算が悪い取引先を一方的に打ち切るような対応を続けると、悪評が広まるリスクもあります。
独立した公認会計士は、クライアントからの信用や評判も重要であるため、仕事とクライアントの選定には注意が必要です。
自由な働き方ができる
3つ目のメリットは、柔軟な働き方ができることです。
公認会計士に限った話ではありませんが、独立後は仕事の進め方やスケジュール管理、働く場所などを自分で決められます。
会社員のように、決まった時間に出社する必要もなく、ライフスタイルに応じた柔軟な働き方を実現できます。
公認会計士が独立するデメリットとは?
次に、公認会計士が独立するデメリットをご紹介します。
安定した固定収入がなくなる
1つ目のデメリットは、安定した固定収入がなくなることです。
独立直後は新規クライアントの開拓やビジネス基盤の構築に時間を要するため、会社員時代のような安定収入を得るのは難しいでしょう。
事業が軌道に乗るまでの期間が長引けば、収入の不安定さが個人の生活や資金計画にも影響を及ぼす可能性があります。
独立準備に必要な費用として、事業に投資するための初期費用やランニングコスト、そして自身の生活費などの費用も備えておくことが重要です。
個人事務所の場合、大型案件は受注しにくい
2つ目のデメリットは、個人事務所の場合、大型案件は受注しにくいことです。
大企業が発注する大規模プロジェクトでは、一定の人員体制や実績、信頼性が求められるため、個人の規模では対応が困難なケースが多くなります。
個人事務所として運営する場合、規模やリソースの限界から、大規模な案件やプロジェクトを受けることは基本的に難しいでしょう。
その分、さまざまな案件を自身の裁量で受けることができるため、ポジティブにとらえれば「スキルセットを多様化できるチャンス」とも考えられます。
孤独感やモチベーションの維持が課題にある
3つ目のデメリットは、孤独感やモチベーションの維持に課題があることです。
独立開業すると、自分自身ですべての物事を決断し、行動する必要があるため、高い自己管理能力と自律性が求められます。
例えば、大企業であれば、定期的に同僚や上司からの助言やフィードバックがありますが、独立するとそのようなサポートもなくなります。
その結果、孤独感が増し、モチベーションの低下やストレス、バーンアウト(燃え尽き症候群)を引き起こす可能性があります。
リラクゼーションやセルフケア、ストレスマネジメントの手法を身につけ、うまく発散することが重要です。
独立派?監査法人勤務派?向いている人の特徴とは
公認会計士の独立と監査法人勤務は、それぞれ求められるスキルや適性が異なります。
独立に向いている人の特徴
独立に向いている公認会計士の特徴は、仕事に対して積極性があり、高い営業力をもっていることです。
独立した公認会計士は、新規ビジネスの機会を見つけ、クライアントを引きつける能力や、仕事の方向性を定めて自己管理する主体性も求められます。
また、精神的に強い人も、独立に向いていると言えるでしょう。
独立という選択は、「不安定さ」「不確実性」を伴うことから、困難や挫折に直面しても、解決策を見出し冷静に対応できる精神的な強さが必要です。
監査法人勤務に向いている人の特徴
監査法人勤務に向いているのは、与えられた業務を期限内で的確にこなせる人です。
また、自分のためだけではなく、組織やチームのプロセスを遵守できる人は、監査法人勤務に向いているでしょう。
さらに、チームで協力しながら大規模な案件に携わりたいと考える人も、監査法人勤務が向いています。
チームでの共同作業を通じて大規模案件に携わる働き方は、独立するとなかなか得難いものです。
公認会計士の独立はいつがいい?最適なタイミングとは
公認会計士が独立するタイミングについて、普遍的な正解はありません。
しかし、一般的には資格取得から5年以上の実務経験を経てからとされています。
公認会計士の資格を取得した時期にもよりますが、平均的な合格年齢が25歳程度というデータを考慮すると、30代半ば頃だと考えられるでしょう。
もちろん、20代で独立する方や、40代まで経験を積んでから独立する方もいます。
年齢にとらわれすぎず、自身のキャリアと市場環境を踏まえて判断することが重要です。
公認会計士が独立前に準備しておくべきこと
次に、公認会計士の独立に向けた準備を解説します。
「税務」の勉強や会計事務所での経験
公認会計士が税理士として独立する場合、税務経験は必須ではありませんが、財務省令で定める研修で税務(税法)的な考え方や税制改正の要点などは習得し、税理士登録する必要があります。
公認会計士の独占業務である「監査」と、税理士の独占業務である「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」を組み合わせ、自身の強みを活かして独立開業することが重要です。
例えば、事業再生、M&A、IPO支援といった分野を主軸として、付加的に税務支援を行うケースも多く見られます。
一般的な税務申告業務はあえて抑え、財務会計コンサルティングを主軸に据えるケースもあります。
クライアント確保のための人脈づくり
公認会計士が独立する際、初期のクライアント確保が大きな課題となります。
そのため、独立前に人脈を築き、潜在的なクライアントとのつながりを作ることが重要です。
特に監査法人などに所属している場合は、クライアントやビジネスパートナーとの関係構築を心がけましょう。
また、近年ではSNSを活用して横のつながりを作っておくことも有効です。
SNSを通じて、自身のスキルや専門知識を共有し、同業の公認会計士と交流できます。
そこで築いた人脈を通じて、新たな案件につながる可能性もあります。
独立した公認会計士の仕事内容とは?
公認会計士が独立する方法は多岐にわたり、独立後の進路によって仕事内容も異なります。
会計事務所の税務業務
公認会計士は所定の研修を受けることで税理士として登録することが可能です。
会計事務所で経験を積んだ後に独立開業する方法は、公認会計士にとって最も一般的な独立形態といえます。
会計事務所を開業した場合の主な業務は、税理士の独占業務である税務申告や記帳代行などの税務対応が中心です。
加えて、財務諸表の作成支援や経営者への財務アドバイス、税務調査対応など、幅広いサポートを行います。
新規事業や投資の計画に対する財務的な評価やアドバイスを行うこともあります。
財務コンサルティング
公認会計士としての監査経験を活かし、財務コンサルティングとして独立する方法もあります。
財務コンサルティングでは、企業の財務戦略の策定や経営課題の解決に向けた助言などが主な仕事内容です。
財務の健全化や収益性向上を目的とした戦略立案・実行支援など、業務範囲は自身のスキルやクライアント業種によって多岐にわたります。
IPO支援系のコンサルティング
IPO支援に特化したコンサルタントとして独立する選択肢もあります。
主な仕事内容は、IPO(新規公開株)を目指す企業に対して、財務状況の監査や財務報告の作成、内部統制・決算開示体制の整備などが挙げられます。
企業がIPOを達成するには、多くの法的・財務的要件を満たす必要があり、専門的な知識が不可欠です。
監査法人での経験と知見を活かし、IPO実現に向けた実務支援やアドバイスを行う存在として、高い信頼を得ることができます。
監査法人の非常勤業務
監査法人に非常勤として所属し、監査業務を行う方法もあります。
常勤職員と比較して、勤務日数や勤務時間など、自由度の高い働き方ができることが大きな特徴です。
税理士登録を行い、会計事務所の運営と並行して監査法人の非常勤業務に携わることで、安定的な収入の確保が可能になります。
また、非常勤業務で監査法人との関係を維持することで、自身の会計事務所の新たなクライアントを獲得できる可能性もあるでしょう。
公認会計士が独立する注意点とは
公認会計士にとって独立開業自体は難しくありませんが、継続的に収益を上げていくには工夫が必要です。
その鍵を握るのが「顧客開拓力」です。
ここで言う「顧客開拓力」は、一般的な「営業力」とは異なる視点が求められます。
営業力とは、見込み顧客へのアプローチや商談、クロージングといった、直接的な販売活動に関わるスキルを指します。
一方で、顧客開拓力とは、業務提携先の選定やマーケティング、ブランディングなど、顧客を獲得するための仕組みを構築する力を指します。
顧客開拓力を身につけていれば、効率的かつ持続的に収益を得ることが可能です。
反対に、顧客開拓力が不足したまま独立すると、戦略のない営業活動に陥り、事務所運営が軌道に乗らないケースも少なくありません。
独立を目指す際は、営業ルートの確立方法や顧客獲得までのプロセスを事前に計画することが不可欠です。
独立に失敗したらどうなるの?
公認会計士が独立に失敗する主な要因は、クライアントを十分に確保できないことです。
営業活動の不備やブランディングの失敗など、失敗の要因は人によって異なります。
結論として、独立に失敗しても監査法人や一般企業などへの再就職は十分に可能です。
独立に失敗するとすべてを失うと考える人もいるかもしれませんが、失うのは事業に限られ、これまで培ったスキルや経験が失われるわけではありません。
スキルや経験が豊富で、かつ比較的若い段階であれば、再就職の可能性は高いといえます。
独立に失敗して再就職を目指す場合は、公認会計士に特化した転職エージェントを有効活用するのが効果的です。
将来独立したい公認会計士歓迎の求人例
弊社MS-Japanで取り扱っている、将来独立を目指す公認会計士向けの求人例をご紹介します。
MS-Japanは管理部門・士業に特化して35年以上の実績がある転職エージェントです。
非公開求人も数多く取り扱っているため、求人紹介を希望される方はぜひ会員登録をしてみてください。
会計事務所から会計士募集(税務未経験可)※将来独立したい方歓迎
| 仕事内容 |
|
・税務顧問業務 ・各種申告書作成業務 ・経営コンサルティング業務 以下、本人のスキルや希望によってアサインします。 ・組織再編 ・事業承継 ・M&Aサポート ・相続の申告 |
| 必要な経験・能力 |
|
・公認会計士有資格 ・税務・経営知識を習得したい方(税務未経験も応募可) |
| 想定年収 |
| 600万円 ~ 800万円 |
中小企業経営に強い会計事務所から税理士・会計士募集※独立志向の方も歓迎
| 仕事内容 |
|
当グループでは、税務・労務を通じて経営者の悩みを取り除き、組織の持続的成長のお手伝いをしています。 税務担当者は、グループ企業である税理士法人(同フロア)へ出向(資格者は在籍)したうえで、月次決算を通じて、経営判断に必要な情報提供と助言を行っていきます。 ・月次決算 ・経営分析資料作成 ・年次決算および申告 ・納税支援および税務届出 ・新規顧客の対応 |
| 必要な経験・能力 |
|
・税理士資格または公認会計士資格 ・資格を活かして、成長を加速させていきたい方 |
| 想定年収 |
| 600万円 ~ 1,200万円 |
【独立志向歓迎】事業再生・M&Aに強いFAS系コンサルティングファームのコンサルタント
| 仕事内容 |
|
・事業再生支援 ・M&A支援 ・事業承継 ・事業・財務戦略策定 ・経営・構造改革など |
| 必要な経験・能力 |
|
下記いずれか必須 ・公認会計士、税理士、USCPA(会計に関する実務経験必須) ・監査業務(監査法人)経験者 ・コンサル業務経験者 ・銀行出身の方 ・事業会社で経営企画、社長室、経理、財務の経験がある方 |
| 想定年収 |
| 500万円 ~ 1,400万円 |
まとめ
公認会計士として独立を目指す場合、監査法人での経験など、ある程度のスキルセットが必須です。
開業初期は収益が安定しにくいため、現職時に人脈を作っておくことが重要になります。
もちろん、独立には不安や失敗はつきものです。
営業活動の不足や差別化の失敗など、さまざまな理由で事業を続けるのが難しくなってしまう可能性もあるでしょう。
ただし、独立に失敗した場合でも、再就職は十分に可能です。
再就職先探しに不安がある場合は、ぜひMS-Japanにご相談ください。
- #公認会計士独立
- #公認会計士独立失敗
- #公認会計士独立準備
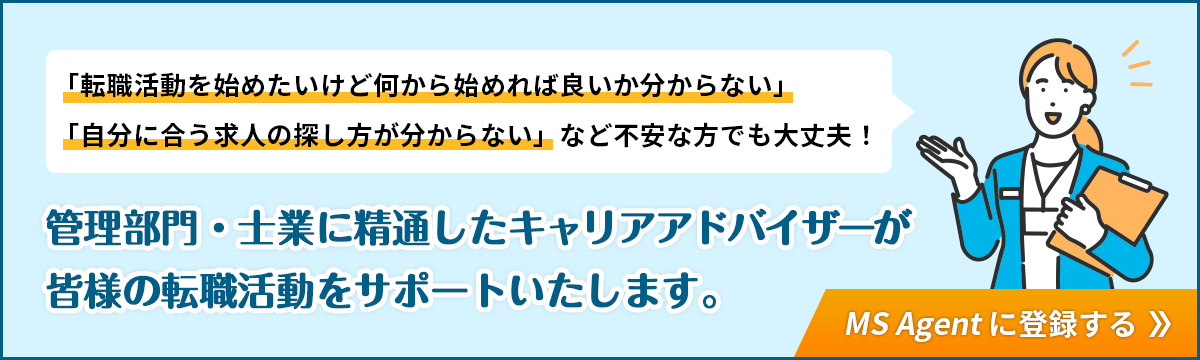
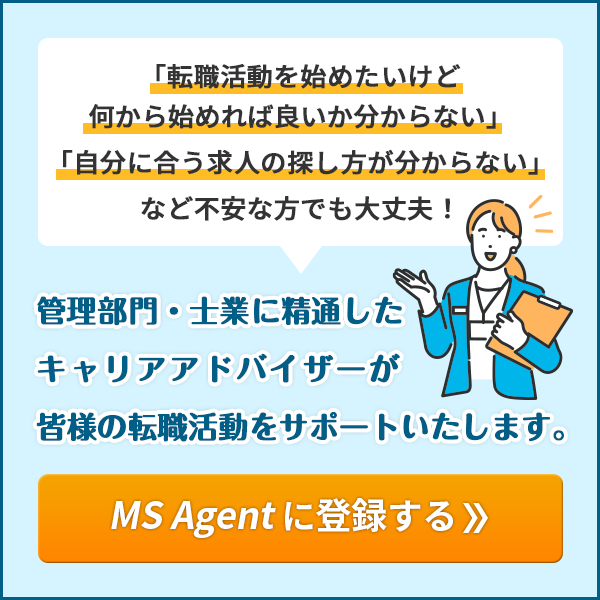 会計士TOPに戻る
会計士TOPに戻る
この記事を監修したキャリアアドバイザー

大学卒業後、カーディーラ・小売業を経験し、2008年からMS-Japanでリクルーティングアドバイザーとキャリアアドバイザーを兼務しております。
会計事務所・監査法人 ・ コンサルティング ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ USCPA ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事

【令和8年公認会計士試験】直近合格率や結果発表後の流れなど

速報【令和8年公認会計士試験|第Ⅰ回短答式試験】最新合格率や結果の推移など

令和8年(2026年)公認会計士試験の日程|試験から合格後の流れ

公認会計士の転職先17選を一挙公開!業界別のキャリア戦略や転職ポイントを徹底解説

公認会計士は副業出来る?おすすめ副業4選と注意点、探し方や求人例まで解説

公認会計士のキャリア/国際税務を理解する30代はなぜ強い?転職市場で評価されるスキルを解説(後編)
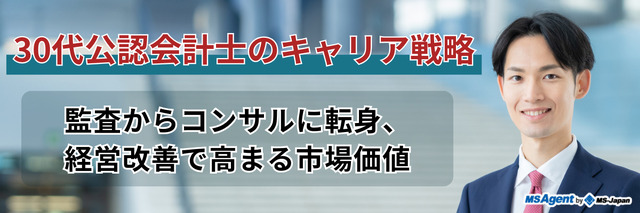
30代公認会計士のキャリア戦略|監査からコンサルに転身、経営改善で高まる市場価値(後編)

公認会計士のキャリア戦略|20代・30代から挑むM&A・財務デューデリジェンス
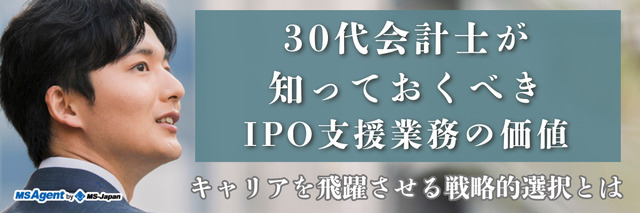
30代会計士が知っておくべきIPO支援業務の価値|キャリアを飛躍させる戦略的選択とは
求人を地域から探す
セミナー・個別相談会
-
はじめてのキャリアカウンセリング
常時開催 ※日曜・祝日を除く -
公認会計士の転職に強いキャリアアドバイザーとの個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く -
USCPA(科目合格者)のための個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く 【平日】10:00スタート~最終受付19:30スタート【土曜】9:00スタート~最終受付18:00スタート -
公認会計士短答式試験合格者のための個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く 【平日】10:00スタート~最終受付19:30スタート【土曜】9:00スタート~最終受付18:00スタート -
初めての転職を成功に導く!転職活動のポイントがわかる個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く
MS-Japanの転職サービスとは
大手上場企業や監査法人、会計事務所(税理士法人)など、公認会計士の幅広いキャリアフィールドをカバーする求人をもとに、公認会計士専門のキャリアアドバイザーがあなたの転職をサポートします。
キャリアカウンセリングや応募書類の添削・作成サポート、面接対策など各種サービスを無料で受けることができるため、転職に不安がある公認会計士の方でも、スムーズに転職活動を進めることができます。

MS-Japanを利用した会計士の
転職成功事例
転職成功事例一覧を見る
会計士の転職・キャリアに関するFAQ
監査法人から事業会社への転職を考えています。MS-Japanには、自分のような転職者はどのくらい登録されていますか。
具体的な人数をお知らせする事は出来ませんが、より直接的に企業に関わりたい、会計の実務経験を積みたいと考えて転職を考える公認会計士の方が大多数です。 その過程で、より多くの企業に関わりたいという方は、アドバイザリーや会計事務所への転職を希望されます。当事者として企業に関わりたい方は事業会社を選択されます。 その意味では、転職を希望する公認会計士の方にとって、監査法人から事業会社への転職というのは、一度は検討する選択肢になるのではないでしょうか。
転職活動の軸が定まらない上、求人数が多く、幅が広いため、絞りきれません。どのような考えを持って転職活動をするべきでしょうか。
キャリアを考えるときには、経験だけではなく、中長期的にどのような人生を歩みたいかを想定する必要があります。 仕事で自己実現を図る方もいれば、仕事以外にも家族やコミュニティへの貢献、パラレルキャリアで自己実現を図る方もいます。ですので、ご自身にとって、何のために仕事をするのかを一度考えてみることをお勧めします。 もし、それが分からないようであれば、転職エージェントのキャリアアドバイザーに貴方の過去・現在・未来の話をじっくり聞いてもらい、頭の中を整理されることをお勧めします。くれぐれも、転職する事だけが目的にならないように気を付けてください。 今後の方針に悩まれた際は、転職エージェントに相談してみることも一つの手かと思います。
ワークライフバランスが取れる転職先は、どのようなものがありますか?
一般事業会社の経理職は、比較的ワークライフバランスを取りやすい為、転職する方が多いです。ただ、昨今では会計事務所、税理士法人、中小監査法人なども働きやすい環境を整備している法人が出てきていますので、選択肢は多様化しています。 また、一般事業会社の経理でも、経理部の人員が足りていなければ恒常的に残業が発生する可能性もございます。一方で、会計事務所、税理士法人、中小監査法人の中には、時短勤務など柔軟に対応している法人も出てきています。ご自身が目指したいキャリアプランに合わせて選択が可能かと思います。
監査法人に勤務している公認会計士です。これまで事業会社の経験は無いのですが、事業会社のCFOや管理部長といった経営管理の責任者にキャリアチェンジして、早く市場価値を高めたいと考えています。 具体的なキャリアパスと、転職した場合の年収水準を教えてください。
事業会社未経験の公認会計士の方が、CFOや管理部長のポジションに早く着くキャリアパスの王道は主に2つです。 一つは、IPO準備のプロジェクトリーダーとして入社し、IPO準備を通じて経営層の信頼を勝ち取り、経理部長、管理部長、CFOと短期間でステップアップする。 もう一つは、投資銀行などでファイナンスのスキルを身に着けて、その後、スタートアップ、IPO準備企業、上場後数年程度のベンチャーにファイナンススキルを活かしてキャリアチェンジすることをお勧めします。近年はCFOに対する期待が、IPO達成ではなく、上場後を見据えた財務戦略・事業戦略となってきているため、後者のパターンでCFOになっていく方が増えています。 年収レンジとしてはざっくりですが800~1500万円くらいでオファーが出るケースが一般的で、フェーズに応じてストックオプション付与もあります。
40歳の会計士です。監査法人以外のキャリアを積みたいのですが、企業や会計事務所でどれくらいのニーズがあるでしょうか。
企業であれば、会計監査のご経験をダイレクトに活かしやすい内部監査の求人でニーズが高いです。経理の募集もございますが、経理実務の経験が無いことがネックになるケースがあります。 会計事務所ですと、アドバイザリー経験の有無によって、ニーズが大きく異なります。また、現職で何らかの責任ある立場についており、転職後の顧客開拓に具体的に活かせるネットワークがある場合は、ニーズがあります。

転職やキャリアの悩みを相談できる!
簡単まずは会員登録