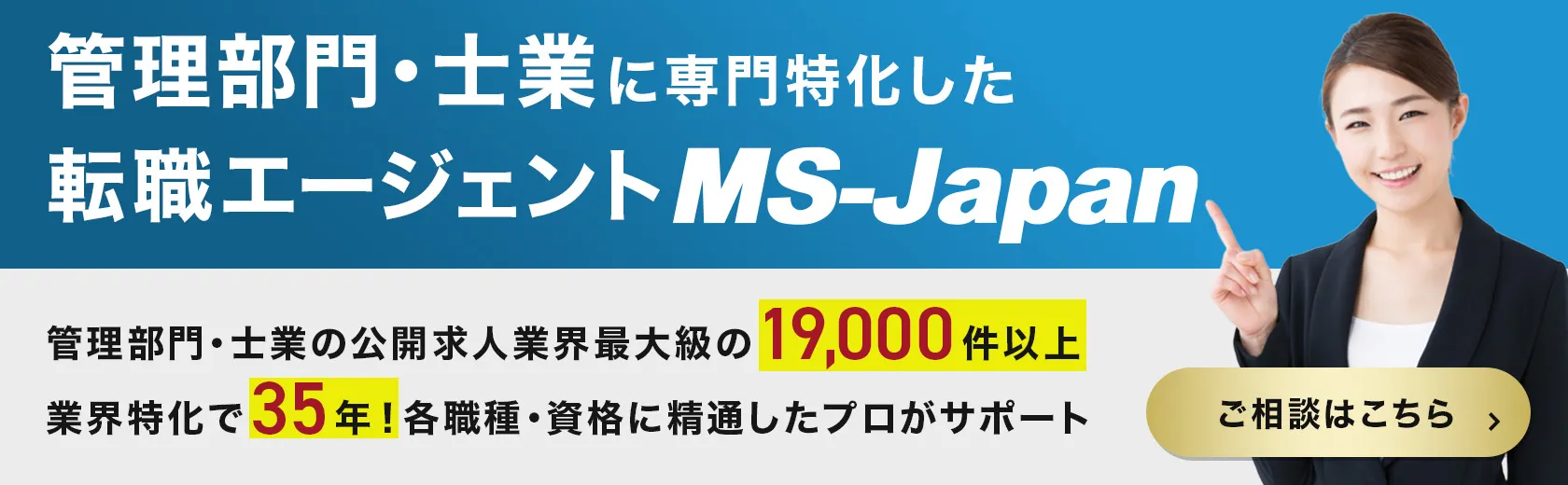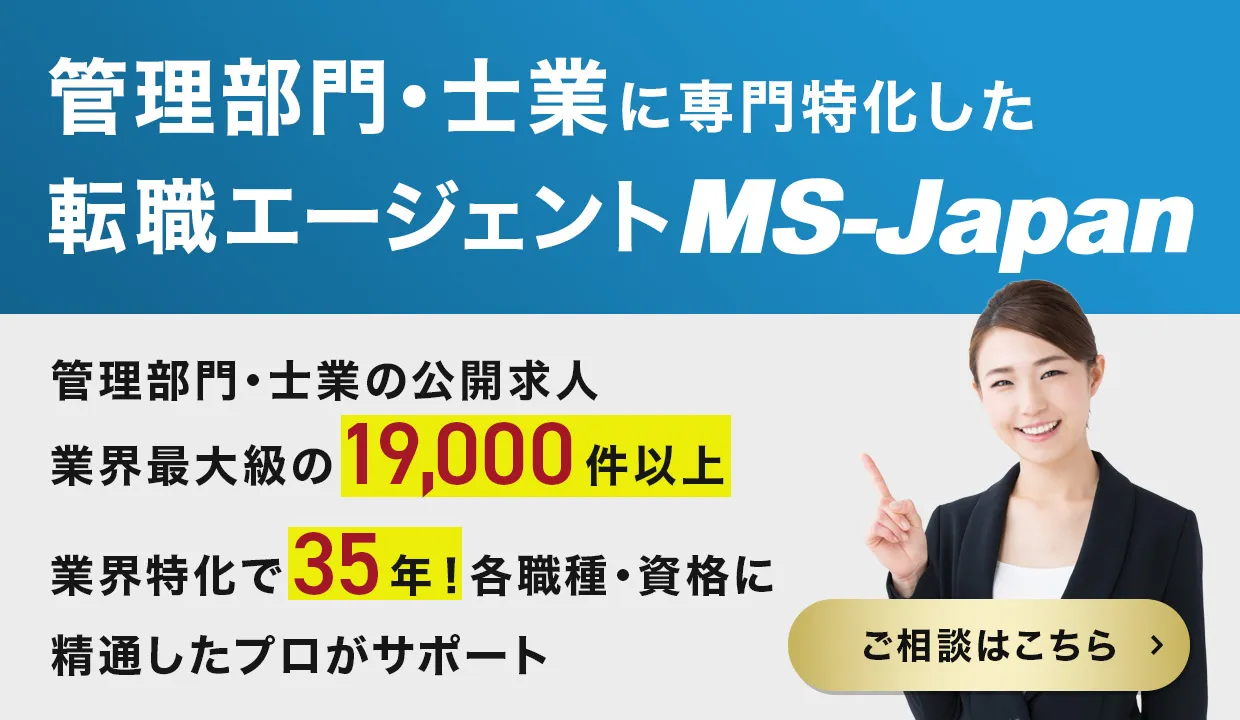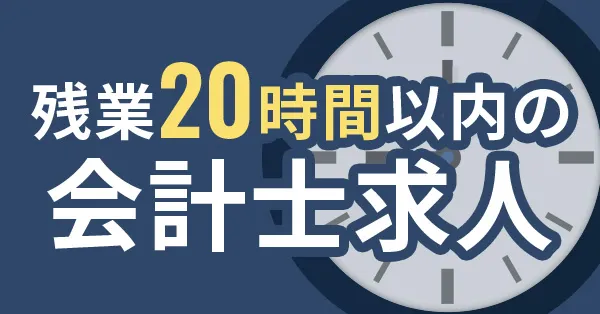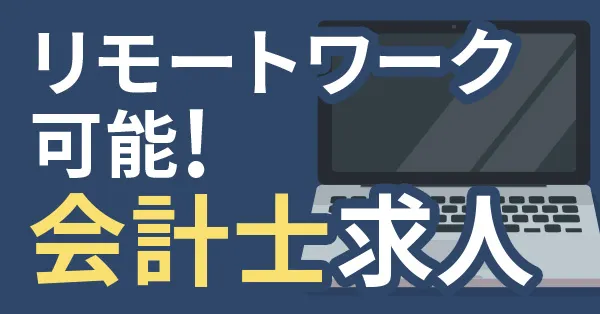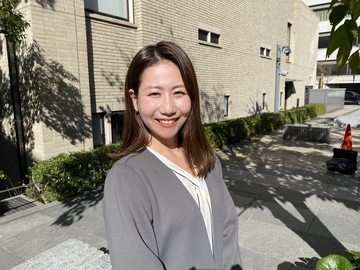監査法人の転職時期はいつが良い?会計士の転職タイミングは?
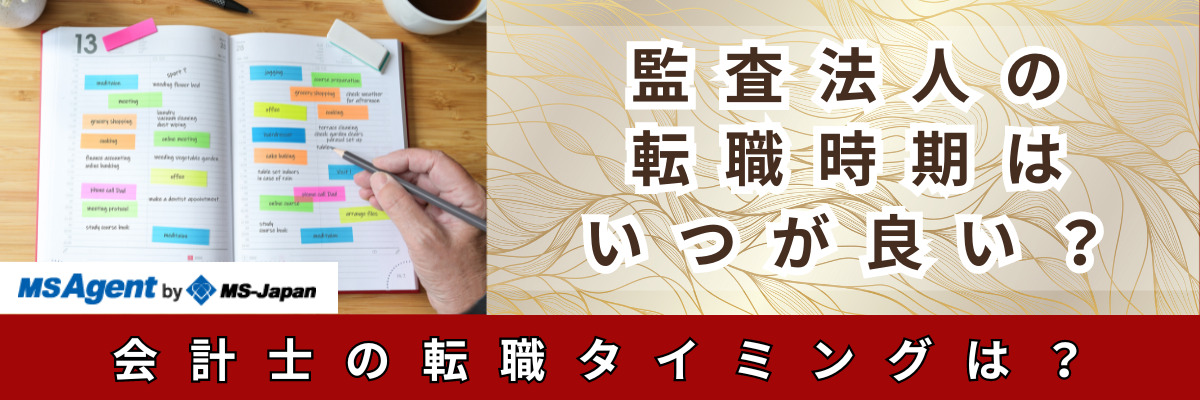
キャリアの中で「転職」という選択肢が一般的になっている昨今、監査法人に勤務している公認会計士の中でも転職を検討している方が増えています。
しかし、実際にいつから転職活動を始めるべきなのか、タイミングに迷っている方が多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、主に監査法人に勤める公認会計士にとってベストな転職タイミング・時期について解説します。
公認会計士は何年目の転職がおすすめ?
監査法人から次のキャリアステップとして転職を考えている場合、監査法人で十分な経験を積んだうえで転職をする必要があります。
では具体的に、監査法人に勤務後、何年目に転職するのが望ましいでしょうか。
3~5年目が最も転職しやすい
監査法人に就職した会計士にとって、入社3~5年目のタイミングが最も転職を考える方が多くなります。
監査業務は3~5年程度で十分なスキル・経験値が身に付くものではないため、監査に強い志向性を見出している方はこの段階で転職を考えてはいません。
よって、このタイミングで転職を考える人は、「監査経験+公認会計士登録を経て、次のキャリア展開を考えている方」です。
日本で公認会計士に登録するには公認会計士試験の合格に加えて、実務経験と実務研修および修了考査が必要であり、そのうちの実務経験をとりあえず現在の監査法人で積めればよいと考えている人もいます。
つまり、実務経験要件を満たして晴れて公認会計士に登録したら、あらためて転職活動をする、というわけです。
入所3~5年目だと20代半ば~30歳前後の年代の人が多く、転職時には将来性を買われてのポテンシャル採用になることも少なくありません。
その場合、採用に当たっては実績・経験よりも今後のキャリアプランが重視されるので、意欲さえあれば転職しやすい時期といえます。
5~10年目もニーズは強い
監査法人で5~10年監査業務に従事すると、大半の方はシニアスタッフに昇格します。
シニアスタッフになると、監査のスケジューリング、手続実施、意見形成などの監査の流れをほぼ把握し、現場の主要戦力として活躍することが求められます。
また、後輩の指導なども任されることも多いです。
そのためこのタイミングでの転職活動においては、経験・実績を積んでいるかどうか、即戦力として活躍できるかどうかが重要になってきます。
応募先の事業所・企業が求める人材ニーズに合致したスキル・経験があれば、スムーズに転職を行えます。
また5~10年目の場合、家庭との両立=ワークライフバランスを重視し、企業内会計士へキャリアチェンジ転職を考える人も増加傾向です。
10年目以降は求人数が少ない
10年目以降になると、年齢も比例して上がるため、転職活動に大きく影響が出てきます。
監査法人の会計士は監査キャリアがメインとなるため、監査法人以外へキャリアチェンジ転職をする場合、未経験領域が多くなればなるほど転職が難しくなる可能性が出てきます。
監査法人内での最終キャリアゴールはパートナーです。
シニア、マネージャ―、シニアマネージャ―と出世、最終的にパートナーになる、というキャリアパスが一般的です。
とは言え、すべての方がパートナーになれるわけでなく、あくまで一握りの優秀な方のみであり、それ以外のスタッフはシニアマネージャ―止まりで定年を迎えることになります。
もし定年まで監査法人で働きたくないと考えているなら、10年目より前の段階で、転職市場のニーズが高いうちに決断するのが望ましいでしょう。
【転職先別】転職タイミングはいつが良い?
公認会計士の転職のタイミングは、どの業種に転職するのかでもおすすめのタイミングが変わります。
この章では、公認会計士の転職先として、「一般企業」、「FAS」、「投資ファンド、戦略コンサル」に分けて転職のタイミングを解説します。
一般企業
大手企業
業界によっても変わってきますが、大手企業での昇進は、入社後7~8年目ほどで主任、入社後10~12年目で課長代理、入社15年目以降で課長といったプロセスになるのが通例です。
コツコツと日々の業務経験を積み重ねることを重視し、その勤務年数に応じて少しずつキャリアが上がっていきます。
こうした組織体系の企業に、監査経験のみをもつ公認会計士が転職活動をしても、なかなか活躍できる機会はありません。
たとえば、監査法人で15年働いた公認会計士の場合、実務経験の年数だけをみると大手企業の課長クラスとなります。
しかし、経験した内容が監査をメインとしている場合、実務経験に乏しいと評価される可能性が高いです。
大手企業の経理部門等で求められるのは主に経理の実務経験であり、監査の経験ではないからです。
企業側が求める経験・スキルがうまくマッチすれば問題ないですが、監査法人での経験がそのまま大手企業の経理部門等で活かせるケースは少ないので、この点は注意が必要です。
また、大手企業で管理職になるには、現場で経験を積むことが前提条件になるのが一般的といえます。
そのため、公認会計士が大手企業に転職し、その後はその企業の経理部門でキャリアを積んでいきたいという場合、30歳前半くらいまでに転職を実現するのが理想的です。
若いうちに転職し、転職先の企業で求められるスキルや経験を積み、将来的に管理職、CFO(最高財務責任者)といったキャリアの道を目指すのが望ましいといえます。
実際、大手企業からの求人も、30歳前半くらいまでの年齢で募集をかけているケースが多くみられます。
なお給与額については、公認会計士だからといって特別高額になることは基本的にありません(資格手当がつく場合はあります)。
その企業の同年齢の水準に合わせられることが多いです。
これらの点を踏まえると、公認会計士が大手企業に転職する場合、30歳前後が適しているといえます。
それよりも若いと社会人としての経験不足の印象をあたえ、それよりも年上だと将来性・成長性という点でより若い人材を選ぶでしょう。
上場企業
大手ではない中堅の上場会社だと、公認会計士の有資格者は総じて重宝される傾向があり、転職のタイミングはそれほど問題にはなりません。
とくに20~30代前半など若い世代が転職する場合、完全な売り手市場です。
ただ、40歳以上になってくると監査法人内ではシニアマネージャ―クラスになっていることが多いため、その年代で中堅の上場企業に転職すると、ほとんどの場合給与が低くなります。
大手であれば給与額のアップ~同水準を条件とすることもできますが、財務体力が限られた中堅の上場企業だとやはり難しくなってきます。
給与水準が下がることは覚悟しておきましょう。
業務内容という点においては、監査法人よりも繁忙度が下がることが多いです。
そのため、多少給与水準が下がってもワークライフバランスを重視したいという場合は、中堅の上場企業は有力な選択肢の1つとして浮上します。
ベンチャー・スタートアップ・IPO準備企業
ベンチャー企業の場合、20代、30代でも好待遇で迎えられるケースが多いです。
30代前半でCFO(最高財務責任者)として転職する人も増えています。
もともとベンチャー企業では経営者自身が20代、30代であることが多く、40代以上の年の離れた人よりも、自分と同世代を採用する傾向があります。
その意味でも、20~30代であっても給与額のアップを目指せる転職先といえるでしょう。
実務経験でいえば、監査法人で3年以上勤務していれば問題なしと判断されることも多いです。
また、ベンチャーでは多くの場合経理体制が未構築であり、公認会計士として就職すると、経理部門の立ち上げを一から任されることもあります。
自ら課題を発見してその解決に取り組み、企業組織の中で実現するというやりがいももてるでしょう。
一方、ベンチャー企業に転職する場合、その企業がどのステージにいるかによって業務内容が違います。
具体的には、創業間もない企業なのか、それともIPO直前の企業であるのかによって、それぞれ公認会計士に求められる役割は変わってきます。
創業間もないベンチャー企業の場合、経理はもちろんのこと、人事や総務、労務といったバックオフィス部門の業務全般を任されるケースが多いです。
その都度関連分野を学び、活用する意識が求められます。
IPO準備企業の場合、一定の実務経験が求められます。
IPO実務を実際に経験しているのが理想ですが、そうではなくても、金融機関や証券会社との折衝などの実務経験があれば転職活動時に有利になるでしょう。
ただし、ベンチャー企業は多産多死の側面もあり、急成長を望める反面、経営自体が難局を迎えるリスクは大手、中堅企業に比べて大きいです。
転職活動を進める際は、この点も踏まえておく必要があるでしょう。
FAS
FASとはFinancial Advisory Serviceの頭文字を取った言葉で、企業の経営者・法務部門・財務部門、金融機関などのクライアントに対し、財務面に関する助言を行うコンサルティングファームのことです。
具体的には、M&A(買収対象会社の調査を行う「デューデリジェンス」等)、事業再生、企業・事業・無形資産等の価値評価、不正リスクマネジメントの構築等に関するアドバイスを行うことが主な業務内容です。
FASへの転職を考える場合、FASの業務に直接かかわるような実務経験をもっている場合だと、30代以降の転職でも成功する可能性は高いといえます。
しかしそのような経験がない場合は、30代に入る前の段階でポテンシャル・将来性をアピールして転職するのが望ましいでしょう。
投資ファンド、戦略コンサル等
投資ファンドや戦略コンサルティングファーム(組織がもつ戦略的課題を解決するための助言を行うコンサル)を対象として転職活動をする場合、監査法人で培った「監査」の業務経験をアピールしても評価にはつながりにくいです。
そのため、監査法人に就職してから投資ファンド・戦略コンサルで実績を伸ばしたいと考えるなら、やはり20代など早い段階で転職を決断するのが合理的といえます。
監査は公認会計士の独占業務であり、そのことが公認会計士資格の価値を高める面をもっています。
しかしそれゆえに、投資ファンドや戦略コンサルティングファームといった他の分野で転職活動をする際、その経験を活かしにくい面があります。
他の分野で競争するなら、やはり求められるスキル・知識・経験で勝負することが必要です。
監査法人でもコンサルティング業務に取り組むことはできるので、将来的に投資ファンドや戦略コンサルティングファームへの転職を考えるなら、コンサルティングの実績を積める機会をできるだけ確保するよう心掛けましょう。
それでも、やはり遅くとも30代前半までが転職の適齢期といえるでしょう。
公認会計士が就職・転職活動する時期はいつが良い?
次に公認会計士が転職をする時期が1年のどのタイミングがおすすめかを解説します。
まずは監査法人で監査業務に従事している公認会計士の場合、往査繁忙期中に転職活動ができる方はほぼいません(面接時間の確保がほぼ不可能な方が多いため)。
そのため、4半期毎に発生する往査繁忙期の間の時期が転職に適した時期となります。
以下が一番多く見受けられる活動パターンです。
通常日系企業は3月末決算先が多いため、会計士の多くは、4~5月に往査繁忙期を迎えます。
その手前の2~3月に活動して3月末までに内定受諾→即退職交渉に入り4月~年度末往査繁忙期の対応をしながら引継ぎ、来期アサインのストップ→6月の監査法人年度末退職、が一番多いパターンでありスムーズに活動が進めやすい時期です(前倒しの入社が可能な場合は企業側の意向に沿って早めに入社されるのがベターです)。
尚、外資系の顧問先や期ズレ先を多く担当されている方、もしくは監査部門ではなくアドバイザリー部門で就業中の方は上記に限りません。
公認会計士は基本的に業務が多忙な方が多いため、転職活動が可能な時期と退職のタイミングを見極めることが重要です。
以下、公認会計士の転職先として候補となる4つの業界を挙げます。
・一般事業会社
・コンサルティングファーム
・会計・税理士事務所
・監査法人
上記における転職に不向きな繫忙期のタイミングについて解説します。
一般事業会社(2~3月、4~5月)
事業会社へ転職する場合は経理・財務、経営企画・内部監査部門などが対象です。
3月末決算企業が多いため、年度末の業務繁忙期は経理部門であれば4・5月、来期の予算編成などが必要な経営企画部門であれば2・3月頃が繁忙期となります。
コンサルティングファーム(年度末)
コンサルティングファームに関しては顧客プロジェクトのアサイン状況によって現場サイドのスケジュールが決まるため、定型的にこの時期という転職のタイミングはとくにありませんが、個々のファームの年度末時期はやはり忙しい時期となるでしょう。
会計事務所・税理士事務所(2~3月、4~5月、12月)
税理士業界は、ご存じのとおり確定申告時期が一番の繁忙期であり、この時期の中途採用については多くの法人・事務所で採用活動を一時的にストップされる場合が多く見受けられます。
上記以外では、3月末決算企業の決算~申告業務が4~5月にかけて、また、12月も年末調整等含め忙しい時期にあたります。
監査法人
マネージャークラスの方が面接対応される機会があるため、往査繁忙期はやはり面接調整が難航する場合があります。
転職活動にはどれぐらい時間がかかる?
上の図は、2023年1月~2023年12月に「MS Agent」を経由して転職決定した公認会計士の転職活動期間のグラフです。
最も割合が多い期間は「31日~60日」ですが、30日以下で転職が決定した方も約2割います。
一方で、転職活動に180日以上かかった方も約1割おり、求職者によって転職活動期間には幅があることが分かります。
さらに、勤務先別の平均転職活動期間を見ると、監査法人を中心とした事務所系は約74日、一般企業(インハウス)は約105日となり、一般企業への転職活動の方が転職決定までに長期間を要する傾向があります。
これは、インハウスへの転職活動では、業界や職種未経験での転職が多く、情報収集や求人探しに時間を要するためと考えられます。
効率よく転職活動を進めたい場合は、公認会計士に強い転職エージェントの活用をおすすめします。
転職エージェントは、公認会計士の転職先として考えられる業界について熟知しており、希望や経験に応じた求人を紹介してくれます。
また、「今すぐ転職したいわけではない」という方でも、転職市場や業界情報を把握しておくことで、いざ転職を決意した際に余裕を持った転職活動を行うことが可能です。
まとめ
公認会計士の転職タイミングは、「時期」と「経験年数」の2つの観点から最適なタイミングを選ぶことが重要です。
転職時期は現職の繁忙期を避けるとともに、応募先企業が求人を募集している時期を狙いましょう。
また、経験年数は3~5年目が転職に適しているとされており、5~10年目のシニアスタッフとしての経験も重要ですが、10年目以降は転職が難しくなります。
転職先の業界や求人によっても最適な転職時期は異なりますので、市場動向を見極めることが転職を成功させるポイントになります。
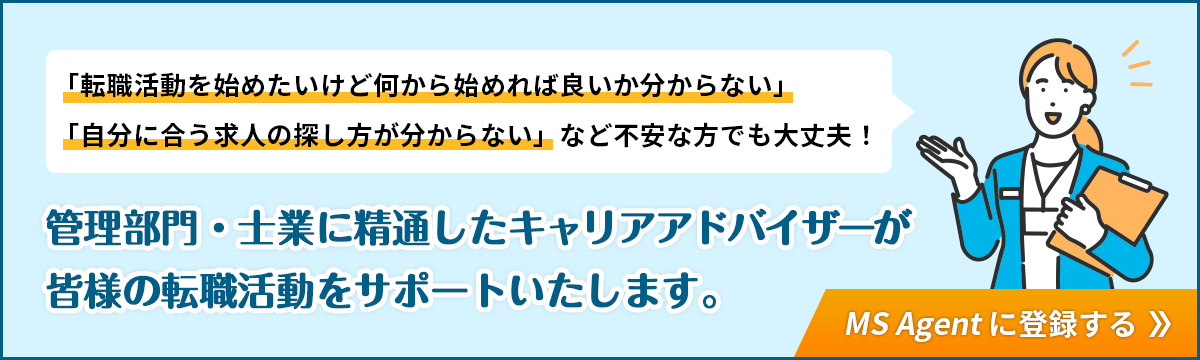
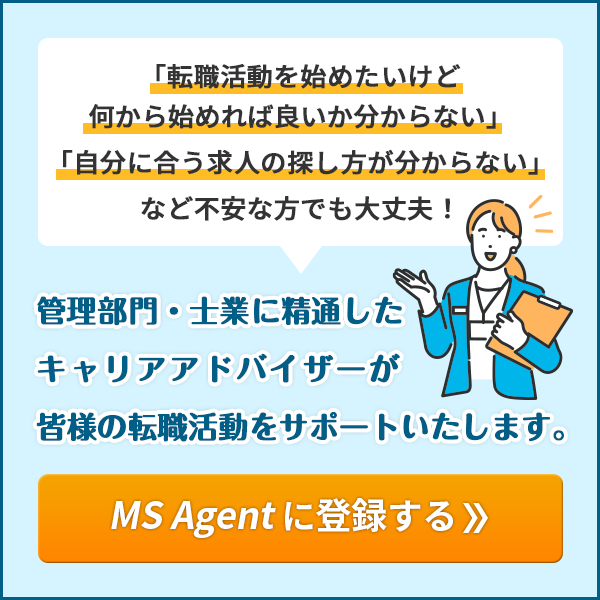 会計士TOPに戻る
会計士TOPに戻る
この記事を監修したキャリアアドバイザー

大学卒業後、食品メーカー営業を経て2005年MS-Japan入社。企業側営業担当を1年半経験し、以降はカウンセラー業務を担当。若手中堅スタッフの方から、40~50代のマネージャー・シニア層の方まで、年齢層問わず年間500名以上をカウンセリングさせていただいています。
企業管理部門全般~会計事務所など士業界、会計士・税理士・弁護士資格者まで弊社の特化領域全般を担当しています。
経理・財務 ・ 人事・総務 ・ 法務 ・ 経営企画・内部監査 ・ 会計事務所・監査法人 ・ 役員・その他 ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事

公認会計士の転職先17選を一挙公開!業界別のキャリア戦略や転職ポイントを徹底解説

公認会計士は副業出来る?おすすめ副業4選と注意点、探し方や求人例まで解説

公認会計士のキャリア/国際税務を理解する30代はなぜ強い?転職市場で評価されるスキルを解説(後編)
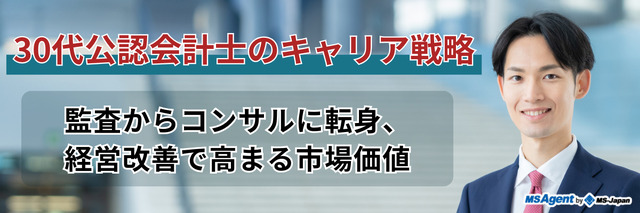
30代公認会計士のキャリア戦略|監査からコンサルに転身、経営改善で高まる市場価値(後編)

公認会計士のキャリア戦略|20代・30代から挑むM&A・財務デューデリジェンス
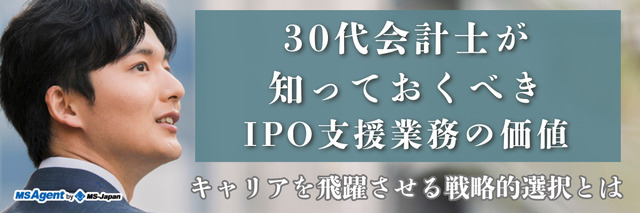
30代会計士が知っておくべきIPO支援業務の価値|キャリアを飛躍させる戦略的選択とは
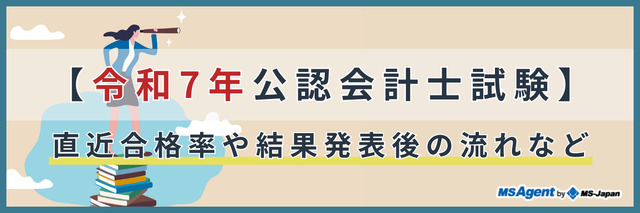
【令和7年公認会計士試験】直近合格率や結果発表後の流れなど
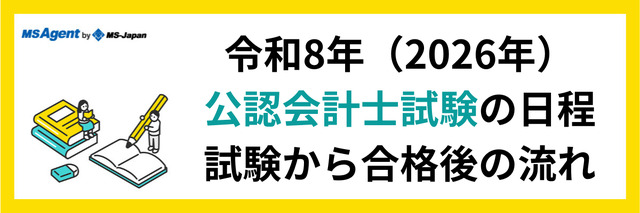
令和8年(2026年)公認会計士試験の日程|試験から合格後の流れ
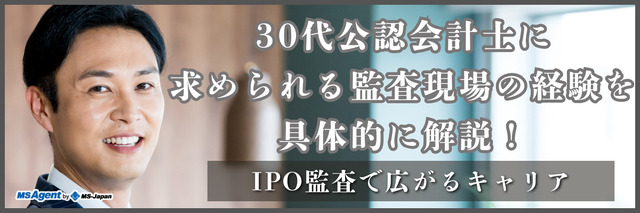
30代公認会計士に求められる監査現場の経験を具体的に解説!IPO監査で広がるキャリア(後編)
求人を地域から探す
セミナー・個別相談会
-
はじめてのキャリアカウンセリング
常時開催 ※日曜・祝日を除く -
公認会計士の転職に強いキャリアアドバイザーとの個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く -
USCPA(科目合格者)のための個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く 【平日】10:00スタート~最終受付19:30スタート【土曜】9:00スタート~最終受付18:00スタート -
公認会計士短答式試験合格者のための個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く 【平日】10:00スタート~最終受付19:30スタート【土曜】9:00スタート~最終受付18:00スタート -
初めての転職を成功に導く!転職活動のポイントがわかる個別相談会
常時開催 ※日曜・祝日を除く
MS-Japanの転職サービスとは
大手上場企業や監査法人、会計事務所(税理士法人)など、公認会計士の幅広いキャリアフィールドをカバーする求人をもとに、公認会計士専門のキャリアアドバイザーがあなたの転職をサポートします。
キャリアカウンセリングや応募書類の添削・作成サポート、面接対策など各種サービスを無料で受けることができるため、転職に不安がある公認会計士の方でも、スムーズに転職活動を進めることができます。

MS-Japanを利用した会計士の
転職成功事例
転職成功事例一覧を見る
会計士の転職・キャリアに関するFAQ
監査法人から事業会社への転職を考えています。MS-Japanには、自分のような転職者はどのくらい登録されていますか。
具体的な人数をお知らせする事は出来ませんが、より直接的に企業に関わりたい、会計の実務経験を積みたいと考えて転職を考える公認会計士の方が大多数です。 その過程で、より多くの企業に関わりたいという方は、アドバイザリーや会計事務所への転職を希望されます。当事者として企業に関わりたい方は事業会社を選択されます。 その意味では、転職を希望する公認会計士の方にとって、監査法人から事業会社への転職というのは、一度は検討する選択肢になるのではないでしょうか。
転職活動の軸が定まらない上、求人数が多く、幅が広いため、絞りきれません。どのような考えを持って転職活動をするべきでしょうか。
キャリアを考えるときには、経験だけではなく、中長期的にどのような人生を歩みたいかを想定する必要があります。 仕事で自己実現を図る方もいれば、仕事以外にも家族やコミュニティへの貢献、パラレルキャリアで自己実現を図る方もいます。ですので、ご自身にとって、何のために仕事をするのかを一度考えてみることをお勧めします。 もし、それが分からないようであれば、転職エージェントのキャリアアドバイザーに貴方の過去・現在・未来の話をじっくり聞いてもらい、頭の中を整理されることをお勧めします。くれぐれも、転職する事だけが目的にならないように気を付けてください。 今後の方針に悩まれた際は、転職エージェントに相談してみることも一つの手かと思います。
ワークライフバランスが取れる転職先は、どのようなものがありますか?
一般事業会社の経理職は、比較的ワークライフバランスを取りやすい為、転職する方が多いです。ただ、昨今では会計事務所、税理士法人、中小監査法人なども働きやすい環境を整備している法人が出てきていますので、選択肢は多様化しています。 また、一般事業会社の経理でも、経理部の人員が足りていなければ恒常的に残業が発生する可能性もございます。一方で、会計事務所、税理士法人、中小監査法人の中には、時短勤務など柔軟に対応している法人も出てきています。ご自身が目指したいキャリアプランに合わせて選択が可能かと思います。
監査法人に勤務している公認会計士です。これまで事業会社の経験は無いのですが、事業会社のCFOや管理部長といった経営管理の責任者にキャリアチェンジして、早く市場価値を高めたいと考えています。 具体的なキャリアパスと、転職した場合の年収水準を教えてください。
事業会社未経験の公認会計士の方が、CFOや管理部長のポジションに早く着くキャリアパスの王道は主に2つです。 一つは、IPO準備のプロジェクトリーダーとして入社し、IPO準備を通じて経営層の信頼を勝ち取り、経理部長、管理部長、CFOと短期間でステップアップする。 もう一つは、投資銀行などでファイナンスのスキルを身に着けて、その後、スタートアップ、IPO準備企業、上場後数年程度のベンチャーにファイナンススキルを活かしてキャリアチェンジすることをお勧めします。近年はCFOに対する期待が、IPO達成ではなく、上場後を見据えた財務戦略・事業戦略となってきているため、後者のパターンでCFOになっていく方が増えています。 年収レンジとしてはざっくりですが800~1500万円くらいでオファーが出るケースが一般的で、フェーズに応じてストックオプション付与もあります。
40歳の会計士です。監査法人以外のキャリアを積みたいのですが、企業や会計事務所でどれくらいのニーズがあるでしょうか。
企業であれば、会計監査のご経験をダイレクトに活かしやすい内部監査の求人でニーズが高いです。経理の募集もございますが、経理実務の経験が無いことがネックになるケースがあります。 会計事務所ですと、アドバイザリー経験の有無によって、ニーズが大きく異なります。また、現職で何らかの責任ある立場についており、転職後の顧客開拓に具体的に活かせるネットワークがある場合は、ニーズがあります。

転職やキャリアの悩みを相談できる!
簡単まずは会員登録